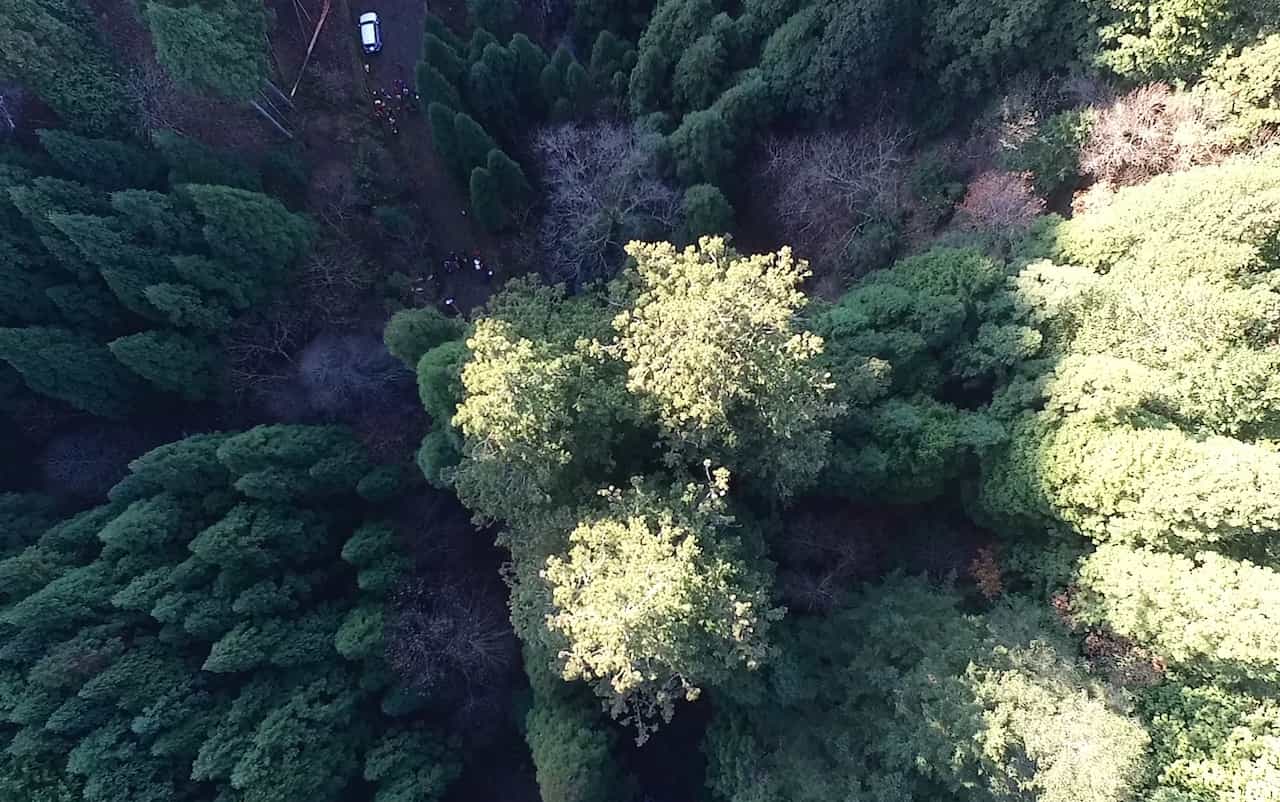京都市内の風景
京都府が発祥!観光におすすめのスポットも
緑茶

宇治田原町の茶畑
日本緑茶の発祥は、京都府南東部に位置する宇治田原町といわれています。名僧・明恵上人の弟子によって栽培方法がもたらされ、霊峰・鷲峰山の麓に位置する「大福谷」に最初の茶の種が植えられたのが始まりです。
そして、江戸時代中頃に、宇治田原町の湯屋谷で茶業を営む「永谷宗円」という人物が15年の歳月をかけて緑茶製法の礎となる「青製煎茶製法」を確立。これにより、庶民も気軽に飲める「緑茶」が誕生しました。
その後、宗円は江戸にわたり、茶商の山本嘉兵衛(のちの山本山)を通じて販売。そのお茶は「天下一」という名で大流行したそうです。以来、宇治田原の茶産業は大きく発展して今日に至ります。
「青製煎茶製法」を編み出した永谷宗円の生家は復元されて現存。実際に使用された焙炉(ほいろ)跡も見学可能です。さらに、この生家のみならず、茶畑や茶問屋、茶農家が混在する湯屋谷の町並みは、2015年に「日本遺産」第1号として認定されています。宇治田原町を訪れる機会があったら、ぜひ湯屋谷を散策してみてくださいね。
任天堂

懐かしいファミコンのコントローラー
任天堂は、1889年に、山内房治郎氏が京都市下京区にて花札の製造を開始したのが始まりです。1902年には、日本初のトランプの製造に着手し、1947年には株式会社丸福(現・任天堂株式会社)を設立。
1963年には、現社名である「任天堂株式会社」に社名変更し、時代の変化に合わせて玩具、電子ゲーム機へと事業を拡大していきました。1983年には「ファミリーコンピュータ(ファミコン)」を発売し、家庭用ゲーム機市場を開拓。今では『スーパーマリオ』や『ゼルダの伝説』など世界的人気を誇るゲームを生み出した、京都発の世界的企業となっています。
任天堂の歴史について詳しく知りたいのなら、2024年にオープンした「ニンテンドーミュージアム」がおすすめ。過去に発売したさまざまな製品が展示されているほか、巨大百人一首で遊べるなど、家族で楽しみながら学べる施設になっています。カフェやショップも併設されており、充実した時間を過ごせますよ。
佐川急便

佐川急便 敦賀営業所
佐川急便の始まりは、1957年に京都市で創業者・佐川清が京都〜大阪間の飛脚業を始めたことにあります。1962年に有限会社、1965年には佐川急便株式会社として法人化され、全国展開を加速。1984年には全国縦貫路線網が完成し、翌年には貨物追跡システムが始まり、さらに1998年には「飛脚宅配便」を正式に開始し宅配市場へ本格参入しました。
2006年にはSGホールディングスを設立して持株会社体制へ移行し、2007年にユニフォームや商品名を刷新。その後も環境対応車やAI、ロボット、自動化技術を導入し、医薬品航空輸送品質認証・幹線共同輸送など多角的に成長。現在も、越境ECや低温物流など新サービスを展開する総合物流企業として進化を続けています。
佐川急便の発祥地・京都の「祇園佐川急便」は一見の価値あり。 祇園の町に溶け込むようデザインされた外観が目を引きます。また、荷物の集配に、従来の大型車両の使用を控え、独自の三輪自動車や台車を使用しているのもポイント。八坂神社から徒歩5分の場所にあるため、観光ついでに訪れたいですね。
みたらし団子

みたらし団子
みたらし団子の起源は、京都市左京区・下鴨神社の境内にある御手洗池とされています。毎年7月の土用になると池底から清水が湧き、水面に浮かぶ泡を模したものが団子の起源という説があるのです。また、串に5つ刺した団子は人の姿に見立てられ、神前に供えた後、醤油をつけてあぶって食べることで厄除けをしたとも伝えられています。
下鴨神社では、土用の丑の頃に御手洗池へ足をつけて無病息災を願う「足つけ神(御手洗祭)」が行われ、夏の風物詩となっています。門前には1922年創業の「加茂みたらし茶屋」があり、黒砂糖ベースのタレを絡めた素朴な甘さの団子が参拝客に人気です。
小学校

「日本最初小学校 栁池校」の石碑
京都は、日本で初めての学区制小学校の発祥地として知られています。1869年、学制発布に先立ち、町衆の寄付により「番組小学校」と呼ばれる民営小学校が64校設立。最初に開校式が行われたのは、「上京第二十七番組(柳池小学校)」と、「下京第十四番組(修徳小学校)」でした。
京都でいう「学区」は、室町時代から続く町組という自治組織が起源。少子化に伴い統廃合が進んだ現在も、祭りや運動会など地域行事ではその伝統が息づいています。京都はまた、女学校・画学校・ろう学校の発祥地でもあり、近代教育をリードしてきた土地です。
京都御池中学校の敷地内には、「日本最初小学校 柳池校」の石碑が建ち、近代教育のルーツを今に伝えています。
京都府京都市中京区柳馬場通御池上る東側(京都御池創生館前))
公式HP:https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/ishibumi/html/na109.html
新撰組

京都守護職・松平容保のもとで京都の治安維持にあたった浪士隊「新選組」は、1863年、京都郊外の壬生村(現・中京区壬生)で、近藤勇・土方歳三・沖田総司などによって結成されました。当初は「壬生浪士組」と呼ばれ、壬生寺や旧前川邸を屯所として剣術稽古と警備活動を行います。
やがて、1864年の池田屋事件で尊王攘夷派を取り締まったことで一躍その名が轟き、幕末京都の治安部隊として強烈な存在感を放つように。京都には上記の壬生寺などをはじめとした新選組にゆかりのあるスポットが点在。街を歩くだけでも、激動の幕末を生き抜いた男たちの生き様に想いを馳せられるでしょう。
絵馬

貴船神社の絵馬
全国に約500社を数える貴船神社の総本宮である貴船神社は、絵馬発祥の地として知られる古社です。677年にはすでに御社殿が存在し、古くから水の神を祀ってきました。
かつては、日照りや長雨が続く際には、朝廷から勅使が派遣され、降雨祈願には黒馬、止雨祈願には白馬を奉納する習わしがあったそうです。平安時代には、その儀式が簡略化され、馬の絵を描いた「板立馬」が代わりに奉納されるようになり、これが絵馬の原型とされています。
貴船神社の境内には、神聖な白馬と黒馬を模した像が並び、訪れる人々に古の祈りの形と信仰の深さを伝えています。
京都の始まりは、日本の文化や歴史の源流となるものが多い!
京都の始まりは、日本の文化や歴史のルーツが多く詰まっています。宇治田原町では永谷宗円が緑茶の作り方を確立し、日本茶文化の基礎を作りました。任天堂は1889年に花札の製造から始まり、今では世界的なゲーム会社になっています。また、みたらし団子の発祥地や、日本で最初の小学校の設立、新撰組の結成など、自然や文化、教育、歴史の始まりが一体となった京都は、日本の原点といえる場所です。
[All photos by PIXTA]