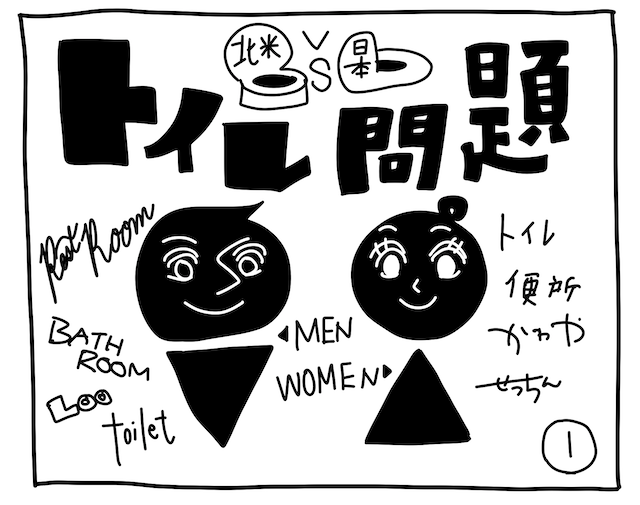飛行機に乗ると、必ずキャビンアテンダントから酸素マスクの使い方のデモがあります。でも、まじめに聴いていない人がほとんどのようです。今回酸素マスクについて調べたら、知らなかったことが沢山ありました。近くフライトの予定がある人は必見です!
まずは知っておきたい機内の気圧

最初に、酸素マスクと切っても切り離せない気圧についてお話ししましょう。飛行機の中の気圧といえば、スナック菓子の袋がパンパンになっているのが思い出されますね。
旅客機は、通常33,000フィート(約10,000m)上空を飛んでいます。地上では1気圧のところ、上空10,000mでは0.2気圧になります。そのままでは人体が耐えられないので、気圧維持装置が作動し、客室内は0.8気圧くらいに調整されています。この気圧は標高2,000m地点にいるようなもの。0.8気圧でさえ、ちょっと酸素が薄いのがお分かりいただけたかと思います。
ちなみに機内を地上と同じ1気圧にするとしたら、機内の外と中の気圧差が大きくなり、飛行機が膨張して壊れてしまいます。それを防止するために壁を厚くすると、今度は機体が重くなってしまうという弊害があるので0.8気圧にしているそうです。
機内の気圧が急低下したらどうなる?

通常、機内の気圧が変化するのは、離陸時と着陸時の15~30分の間のこと。
先日、インドの航空会社であるジェット・エアウェイズの国内線フライトで、パイロットが気圧維持装置を作動し忘れるという事故がありました。どうなったかと言うと、乗客166人のうち30人が耳や鼻から出血したそう。その後、旅客機は空港に引き返したそうです。
キャビンの気圧が下がると、天井から酸素マスクが下りてきます。このときパイロットは、人体に安全な高度である10,000フィート(3,048m)以下まで機体が急降下するよう操作します。乗客側には、まるでジェットコースターに乗っているような動きで生きた心地がしないかと思いますが、コントロールを失ったわけではないので落ち着きましょう。ちなみに、飛行中に機体に穴が開くなどして気圧が急激に下がっても、それで墜落ってことはまずないということです。
もし上空40,000フィート(12,192m)にいるときに機外と同じ気圧にさらされたら、猛烈な酸素不足の状態になり、正常に意識を保てる時間(有効意識時間)は18秒ほど。それを過ぎると意識を失い、脳の損傷や死に至ることもあるんです。そのため、酸素マスクが作動している間に、機体を急降下させる必要があるんですね。
酸素マスクについて知っておきたいこと

そんな重要な酸素マスクですが、客室の酸素マスクから出てくる酸素はどのように保存されていると思いますか?
酸素のタンクは重くてかさ張るので、全員分の酸素を機体に載せられません。そのため、酸素はその場でつくられるんです。各座席のパネルの上に、化学物質の混合物が収められています。酸素マスクのコードを引っ張ると化学プロセスが起こります。物質が燃えて、酸素がつくられるということです。一旦出たら、最後まで出っぱなしになります。酸素が出てくるのは、12~15分程度と言われています。
さて、酸素マスクについてぜひ覚えておいていただきたいことが3点あります。
- 酸素マスクのバッグは膨らまないもの
- 酸素発生機が非常に熱くなるので触らない
- 燃えている臭いがしても、気にしなくてOK
酸素マスクのバッグが膨らまないので壊れていると早合点して、マスクを使わずに低酸素症(頭痛、吐き気等)になった人たちがいたそうです。さらに、酸素は燃やしてつくるものと知っておけば、熱くなるのに気を付けられるし、燃えている臭いがしても慌てないで済むでしょう。
また、酸素マスクの使い方を間違っている人が非常に多いそうなので、次回のフライトではしっかりデモをみて万一に備えましょう。
参考
[The Telegraph]
[JIJI.COM]
[Solaseed Air]
[JAL]