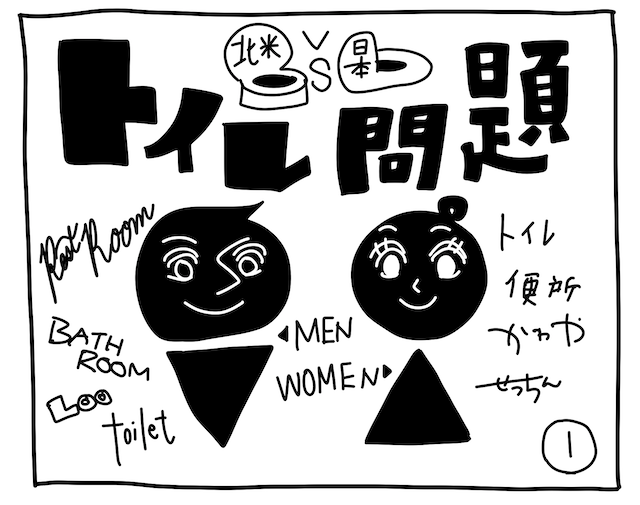6月5日の日本気象協会の記事によると、梅雨前線が例年通り北上しており、近畿や関東も今週末から梅雨入りする可能性があるそうです。ところで毎年、この時期になると、頭痛や倦怠感、疲れを感じる人もいるのではないでしょうか。その原因は「梅雨バテ」かもしれません。
そこで株式会社リーフェ代表取締役社長であり、現役医師の橋下将吉(はしもとまさよし)さんの「梅雨バテ対策セミナー」に参加。「梅雨バテ」の原因と対策について聞いてきました。
そもそも梅雨バテって何?
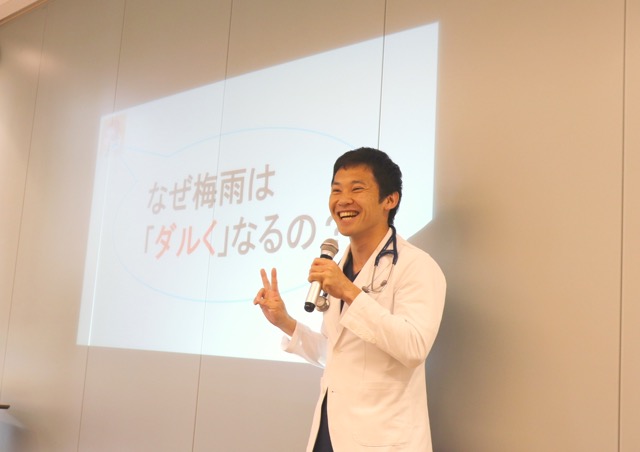
皆さんもご存知の通り、冬は空気が乾燥することで、インフルエンザウイルスに感染しやすくなります。季節(環境)と病気は非常に関係性があるんです。
ですが「梅雨バテ」は医学用語ではありません。イメージがわきやすいため、梅雨に起こる症状をまとめて「梅雨バテ」と言うのだそうです。
梅雨バテの具体的な症状としては「頭痛」「倦怠感」「疲れ」などがあります。梅雨の時期のように、湿度と温度が高いと、人は体外に熱を逃がせなくなり、このような症状が出やすくなるとのこと。
どうして梅雨バテになるのか?

人間の自律神経には副交感神経と交感神経の2種類があります。梅雨の時期は副交感神経(内臓を休ませる)よりも交感神経(内臓を動かす)の方が高ぶってしまうのだそうです。
わかりやすく例えると、走った後は体が熱くなり、発汗します。その汗が蒸発すると体が冷えたように感じますよね。人は発汗によって、体の熱を冷ましているんです。しかし、梅雨の季節は気温と湿度が高いので、汗が蒸発しづらくなり、体の熱を逃がせなくなってしまいます。
体から熱が逃げない状態が続くと、どんどん汗をかき、脱水症状になってしまうことも!
まとめると、梅雨という気象の変化が、交感神経の緊張や軽度の脱水症状など人体にさまざまな影響を及ぼす・・・それが「梅雨バテ」なんです。
今すぐできる、梅雨バテ対策

「生活環境を変える」
暑すぎず寒すぎない温度に室温を設定します(26〜28度がオススメ)。湿度の高さも梅雨バテの原因になりますので、除湿器を稼働させるのもひとつの手です。また、高温多湿な環境にはカビが発生しやすくなるため、マメに家を掃除することも大切。
「食べ物を整える」
東洋医学から見ると、旬の物を食べることが大事。今の時期であれば、スイカ、ビワ、さくらんぼなどを食べると良いです。さらに食べ物の品目数を意識して、バランスよく栄養を摂ることも忘れないようにしましょう。
「運動をする」
体に熱をためやすい梅雨の時期は、脂肪や筋肉量が多い人は特に注意が必要です。体外に熱を逃しにくくなり、熱中症になりやすくなります。体に脂肪を溜め込まないためにも、有酸素運動をして脂肪を燃焼させ、無酸素運動をして筋肉を鍛えるといいでしょう。有酸素運動と無酸素運動のどちらも、バランス良く組み合わせて行うことが大切です。
「スペシャルドリンクを飲む」
かつて世界で猛威をふるっていたコレラウイルスは人間が死ぬまでお腹を下す、非常に危険なウイルスです。コレラに感染すると、ウイルスが体外に排出されるまで水分を摂取し続けなくてはいけません。
しかし、コレラ発生地が僻地だったり、患者が水を飲めない状態の場合、とりあえず摂取しておけばいいと言われているのが、OS-1や経口補水液と言われるものです。
じつはこのスペシャルドリンクを自宅で簡単に作ることができます。
サッパリと飲みやすい、スペシャルドリンクの作り方

材料
レモン・・・大さじ1
リンゴ酢・・・小さじ1
オリゴ糖・・・大さじ1
はちみつ・・・大さじ1+小さじ1
塩・・・ひとつまみ
オススメの合わせ食材は、夏のフルーツであるビワやパイナップル、桃、ライチ、メロンや梅やミントの葉です。好みのフルーツや食材を入れて、スペシャルドリンクを作ってみるといいでしょう。

筆者はパイナップルと桃を入れて飲んでみましたが、甘すぎず、さっぱりとしていてとても飲みやすかったです。フルーツを入れるので、ちょっとしたデザート代わりにもなります。
旅行や予定がある日に「梅雨バテ」になってしまうと、悲しい気持ちになってしまいますよね。そのせいで、せっかくのプランが台無しになってしまうことも。そうならないためにも、今のうちから「梅雨バテ対策」をしておきたいですね。
HP:https://li-fe.tokyo/
「医学」×「健康」×「時事ネタ」健康解説動画チャンネル「からだプラン」
You Tubeチャンネル:
https://www.youtube.com/channel/UCsulu2ghMsPVFeI5yVcb6aQ
[Photos by あやみ & Shutterstock.com]