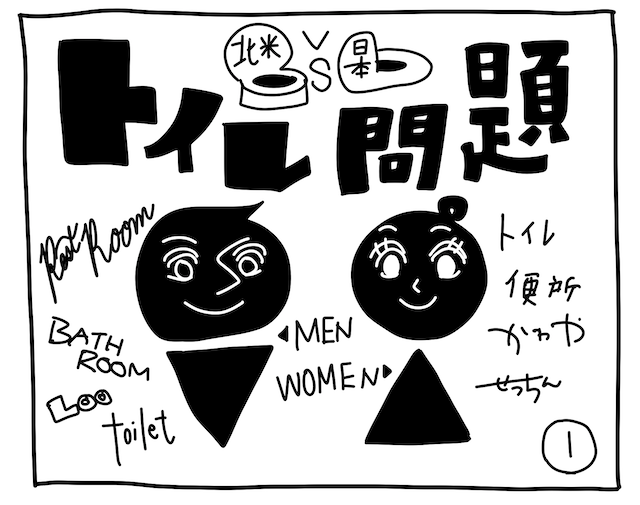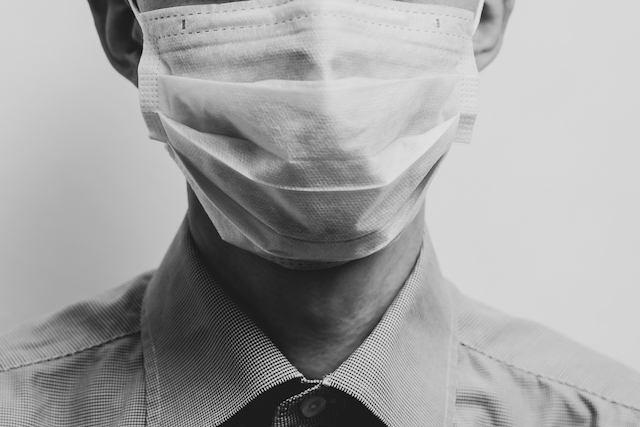
マスクの始まりは19世紀の末、欧米から

調べてみると、マスクには原義に「道化者」という意味があるそうです。マスクには「仮面」という意味もあります。確かに仮面を被ると、ちょっと普通ではない見た目になりますよね。衛生用品のマスクもある意味で同じかもしれません。
このマスクが医療用品としての役割を持ち始める時期は、19世紀の末。舞台は欧米各国です。米Bloombergの記事によると、ニューヨークの内科医A.J. Jessupが1878年(明治11年)、論文でコットンのマスク着用による伝染病の感染予防を主張しました。
その後、1897年(明治30年)にも、外科手術中にマスクの着用を訴える論文が発表され、さらに1905年(明治38年)には、シカゴの内科医Alice Hamiltonが、あらためて手術中のマスク着用を論文で訴えます。
発疹性感染症(しょうこう熱)の患者が泣いたり、せきをしたりすると、どれくらい菌が飛散するのか、 健康な(無症状の)医師や看護師がしゃべったり、せきをしたりすると、どれくらいの連鎖球菌が飛散するのか、論文で明らかにしたのですね。

さらに1910年(明治43年)には、歴史を変える動きが起こります。当時ペストが流行していた満州(現在の中国の一部)に招かれた内科医Wu Lien-Tehが、空気感染のリスクを訴え、医療従事者や一般の市民が装着できるマスクを開発し、広めようとしたのですね。
そのマスクは、従来のマスクよりも層を厚くし、さらに屋外でも着用できるようなフィット感がプラスされていました。
こうした歴史が積み重なり、後の1918年(大正7年)に世界的な流行を見せたスペイン風邪を機に、マスクの着用が一気に世界に広がるのですね。
日本でマスクが広まった時期は大正時代

日本へのマスクの紹介は、ここまでに述べたマスクの世界史と歴史を共にしています。一般社団法人日本衛生材料工業連合会によれば、日本には明治の初期にすでに海外からマスクが入ってきていると言います。
ただし、最初のマスクは医療用というよりも、粉じんを防ぐための作業用。金網の芯に布地をフィルターとして取り付けたタイプだったと言います。
その日本で、本格的に衛生用品としてマスクが使用される時期は、世界と同じ1918年(大正7年)のスペイン風邪の大流行がきっかけとなります。スペイン風邪はスパニッシュ・インフルエンザとも言われ、国内で大流行したインフルエンザです。国内だけで約38万5000人が亡くなりました。
筆者もこのスペイン風邪について、別媒体で記事にした経験があります。各府県ではマスクの着用が一般市民にさまざまな形(ポスターや街宣カーによるアナウンス、劇場でのコマーシャルなど)で啓もうされ、一気にマスクが浸透していったと、さまざまな記録が残っていました。
この後、度重なるインフルエンザの流行とともに、マスクは着実に市民の間に広まっていきます。その過程で、布マスクがガーゼマスクになり、花粉症の流行とともに、日本人にとって手放せない衛生用品となっていくのですね。
以上、簡単ですが、マスクの大まかな歴史でした。ちなみに欧米各国でマスクが生まれ、広まっていく過程で、最初はほとんどの医療従事者が、マスクの着用を笑い、拒否したと言います。
しかし、時の経過とともにその役割が認められ、世界に浸透していったマスク。先人の知恵をきちんと受け継ぎながら、現代の生活に上手に取り入れていきたいですね。
[参考]
※ Pandemics Come and Go But Medical Masks Are Eternal – Bloomberg