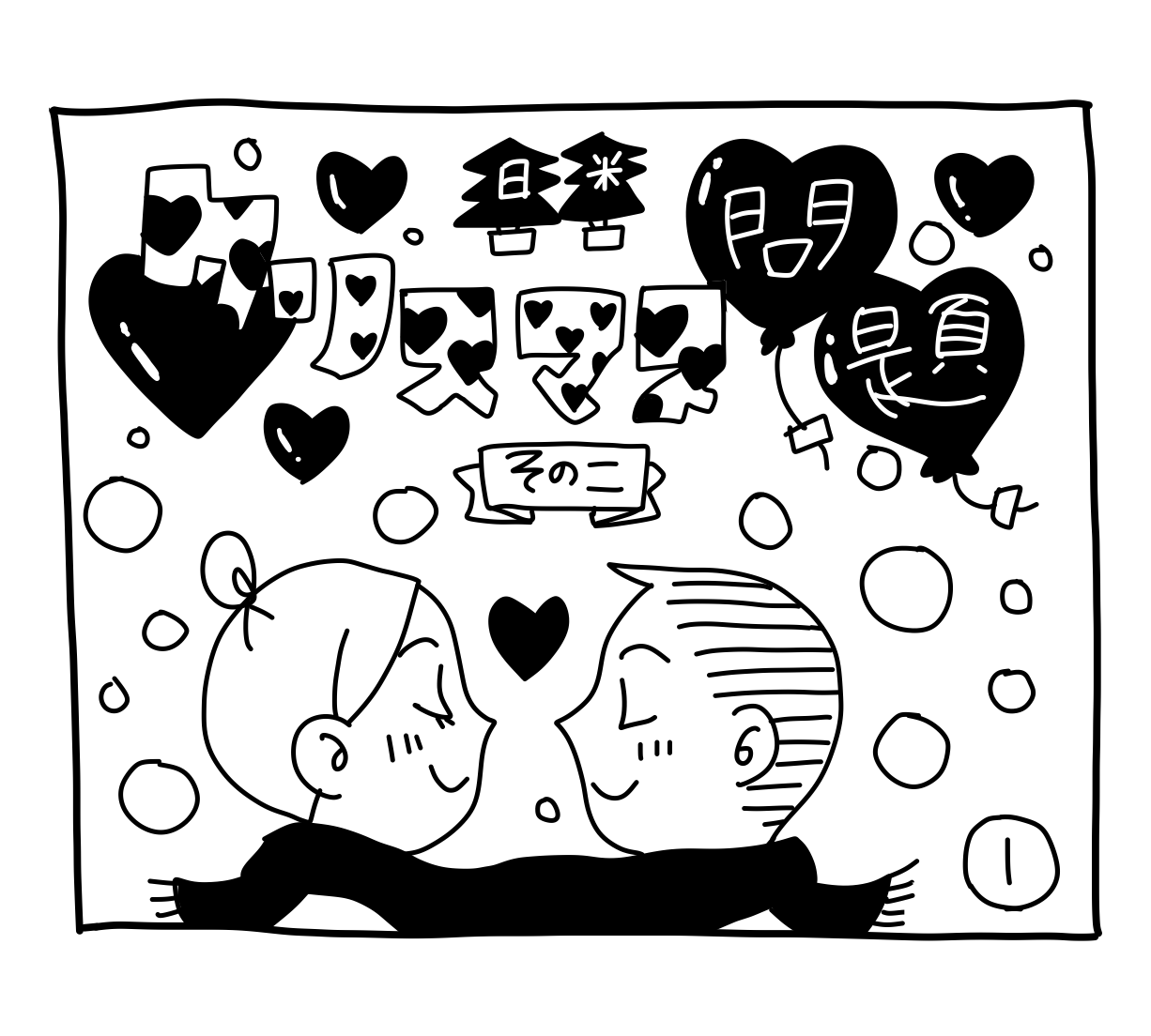北海道・東北エリア
北海道:冬でも家の中では半袖
青森県:雪が多い
岩手県:捨てることを「投げる」と言う
宮城県:七夕祭りを8月に行う
秋田県:修学旅行の安否確認情報がCMで流れる
山形県:雑草のひょう(スベリヒユ)を食べる
福島県:朝からラーメンを食べる

仙台七夕まつり
北海道・東北エリアで選出されたのは上記です。北海道の「冬でも家の中は半袖」は、寒冷地ならではの住まいの工夫が理由。高断熱・高気密に優れた住宅に加え、セントラルヒーティングなど全館暖房の普及により、家の中はとても暖かいのです。宮城県で七夕祭りが8月に行われている理由は、お盆と稲作の豊作を祈願するためで、全国的にも有名な「仙台七夕まつり」は、毎年8月6日〜8日に開催されています。

福島県の喜多方ラーメン
また、山形県で雑草のひょう(スベリヒユ)が食べられているのは、豪雪地帯ゆえに冬場の食糧確保が課題だった背景から、春〜秋に採れる山菜や野草を塩漬けにする「保存食文化」が根づいており、その名残なのだとか。福島県の「朝からラーメン(通称・朝ラー)」もインパクト大。これは、夜勤明けの工場勤務の人や、早朝に農作業を終えた農家の人たちが、朝の一杯としてラーメンを食べていたことに由来するという説があり、今でもその文化が根づいています。
関東エリア
茨城県:メロンの生産量が多い
栃木県:雷が多い
群馬県:上毛かるたをほとんどの人が知っている
埼玉県:小学校で出席を取るときに「はい、元気です」と言う
千葉県:落花生を茹でて食べる
東京都:通勤時の満員電車
神奈川県:横浜に都市型ロープウェーがある

メロン
関東エリアで選ばれたのは上記の「驚かれること」。茨城県は実はメロン王国です。生産量・消費量ともに全国1位を誇り、県オリジナル品種「イバラキング」をはじめ、「オトメ」「アンデス」「クインシー」など、さまざまな品種が栽培されています。群馬県の「上毛かるた」は、県民なら誰もが知るローカル文化。1947年に誕生し、群馬の名所や偉人などが札になった全44枚の郷土かるたで、学校の授業や大会でも使われるなど、今では群馬のアイデンティティの一部です。

YOKOHAMA AIR CABIN(ヨコハマ エア キャビン)
埼玉県では、小学校で出席を取るときに生徒が「はい、元気です」と返事をするのが定番。これは、先生が出席と同時に子どもの体調を確認するために始まったといわれています。千葉県では、落花生を「塩ゆで」で食べるのが一般的。ホクホクした甘みを楽しめる茹で落花生は、ご当地グルメとして人気です。そして神奈川県・横浜の「YOKOHAMA AIR CABIN(ヨコハマ エア キャビン)」は、都市型ロープウェーとして注目の存在。桜木町駅と運河パークを結び、空中からみなとみらいの街並みを一望できます。
北陸・甲信越エリア
新潟県:信号機が縦型
富山県:持ち家率が高い
石川県:住所にカタカナ一文字の表記がある
福井県:「早くしなさい」を「はよしねま」と言う
山梨県:「無尽」という文化がある
長野県:イナゴや蜂の幼虫を佃煮にして食べる

新潟県の信号機
北陸・甲信越エリアから選出されたのは上記一覧です。新潟県では、信号機の多くが縦型になっているのが特徴。これは豪雪地帯ならではの工夫で、横型に比べて雪が積もる面積が少なく、重みで信号が壊れたり、信号が見えなくなったりすることを防ぐためです。富山県は、全国的に見ても持ち家率が非常に高い県。共働き正規雇用世帯の割合が高く、勤労者世帯の実収入もトップクラスです。加えて、親から土地を譲り受けるケースも多く、マイホームを持つ環境が整っています。

※画像はイメージです
山梨県の「無尽(むじん)」は、もともとはお金を持ち寄って融資し合う互助制度でしたが、現在では飲み会や旅行といった「定期的に仲間と楽しむ会」として定着。グループごとに独自のスタイルがあり、共通するのは「仲間とおいしいお酒や料理を楽しむ」ということです。長野県には、イナゴや蜂の幼虫を佃煮にして食べる食文化が今も残っています。かつては山間部でタンパク源が限られていたことから、虫が貴重なタンパク源だったことに由来。特に南信地方の伊那谷では、今でもこの風習が根づいています。
東海エリア
岐阜県:自転車を「ケッタマシーン」と呼ぶ
静岡県:おでんの汁が黒い
愛知県:学校の休み時間を「放課」と呼ぶ
三重県:明明後日を「ささって」という

静岡おでん
東海エリアではこれらの「驚くこと」が選出されました。岐阜県の自転車のことを「ケッタマシーン」と呼ぶのは、「ケッタ」という比較的新しい方言に由来。「ケッタ」の語源は「蹴りたくる」とされています。静岡県のおでんの汁が黒いのは、濃口醤油などで味つけし、長年かけて継ぎ足していくためです。

学校の休み時間
愛知県では、学校の休み時間を「放課」といいます。「20分休み」を「20分放課」のようにいい、これは名古屋弁や三河弁の一部。また、三重県では「明明後日(しあさって)」のことを「ささって」といいます。方言の奥深さを感じますね。
近畿エリア
滋賀県:琵琶湖の面積は県の面積の6分の1
京都府:パンが好きな人が多い
大阪府:語尾に「知らんけど」をつける
兵庫県:小学校が土足制
奈良県:雑煮の餅にきな粉をつけて食べる
和歌山県:ラーメンと早寿司(しめ鯖などの押し寿司)を一緒に食べる
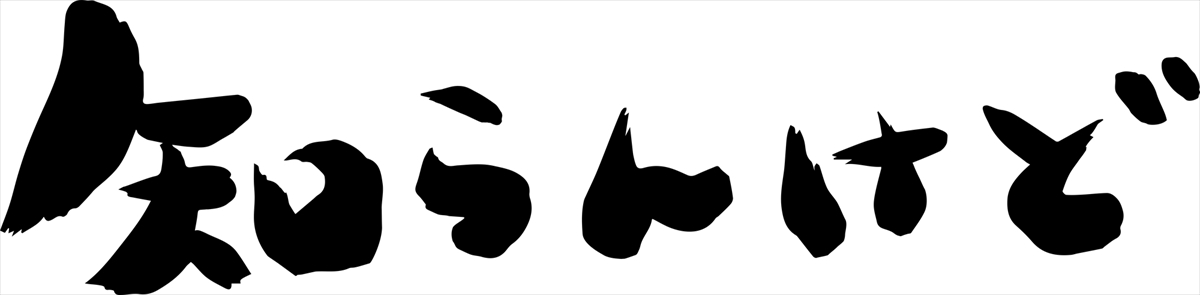
滋賀県の約6分の1が琵琶湖というのは、地図で見ると一目瞭然です。京都は意外にもパン好きが多く、パンの消費量やパン屋の数が全国トップクラス。おしゃれなパン屋さんが多いのも納得です。大阪府の語尾に「知らんけど」をつけるは、2022年の流行語大賞にもトップ10入りし、全国に広がっています。

※画像はイメージです
兵庫県(特に神戸市)では、小学校が土足制の学校が多いのが特徴的。もともとは人口急増による校舎不足から、午前・午後の二部制授業が行われていた背景があり、靴箱のスペースが取れなかったためといわれています。また、外国人居留地があった影響もあり、土足文化が比較的なじみやすかったようです。教室の床は「油引き(ワックスがけ)」をして、砂ぼこりを防いでいます。
中国・四国エリア
鳥取県:正月の雑煮がお汁粉
島根県:法事であんぱんを配る
岡山県:晴れの日が多い
広島県:お盆にお墓の周りにカラフルな盆提灯を飾る
山口県:ガードレールが黄色い
徳島県:赤飯にごま砂糖をかけて食べる
香川県:雑煮の餅があん入り
愛媛県:少年式(14歳になった少年少女を祝う式典)がある
高知県:おきゃく(宴会)文化がある

カラフルな盆提灯
島根県では、法事の際に配るあんぱん「法事パン」が定番。鳥取県や岡山北部にも見られる風習で、地元のパン屋やスーパーではごく普通に販売されています。ルーツは「あんこ餅」といわれており、甘いもので故人を偲ぶ文化です。広島県西部では、お盆になると墓地に色とりどりの「盆灯籠(ぼんとうろう)」を飾る風習があります。夜には灯りがともされ、幻想的な雰囲気に包まれます。

山口県のガードレール
山口県のガードレールが黄色いのは、県の特産品である夏みかんの色にちなんでいるのだとか! 山の緑に映えて視認性が良いのもポイントです。愛媛県の「少年式」は、14歳の節目を祝う珍しい行事。かつての「元服」にあたる儀式として、地域によっては海に海草を投げ入れる伝統なども残っています。
九州・沖縄エリア
福岡県:夜にゴミ収集がある
佐賀県:ラーメンに生卵が入っている
長崎県:自転車に乗れない人が多い
熊本県:「あとぜき」(開けた扉は閉めましょう)という言葉が使われる
大分県:自宅に温泉がある家がある
宮崎県:運動会の組分けを赤団、白団と呼ぶ
鹿児島県:桜島の噴火が日常茶飯事
沖縄県:結婚式の招待客が多い

オランダ坂
九州・沖縄エリアの驚くことに挙げらえたのは上記。福岡市では夜(日没から夜12時)にゴミ収集が行なわれています。これは、交通渋滞の緩和や、カラスによるごみ荒らし対策などの理由から。長崎県で自転車に乗れない人の割合が多いのは、特に長崎市に坂道や階段が多いことが関係しているとか。

※画像はイメージです/p>
また、熊本県の「あとぜき」とは、開けたドアをしっかり閉めましょう、という意味の方言。「ぜき」は古語の「せく(堰く・塞く)」からきているといわれています。沖縄県では、結婚式の規模がとにかく大きい! 平均で200~300人、多いと500人もの招待客が集まることもあります。会場入りしてすぐにお酒が振る舞われ、卓盛り(テーブルごとに大皿料理)形式の豪華な料理が提供されるのも特徴です。
[参考]
ソニー生命「47都道府県別 生活意識調査2024」
[All photos by PIXTA]