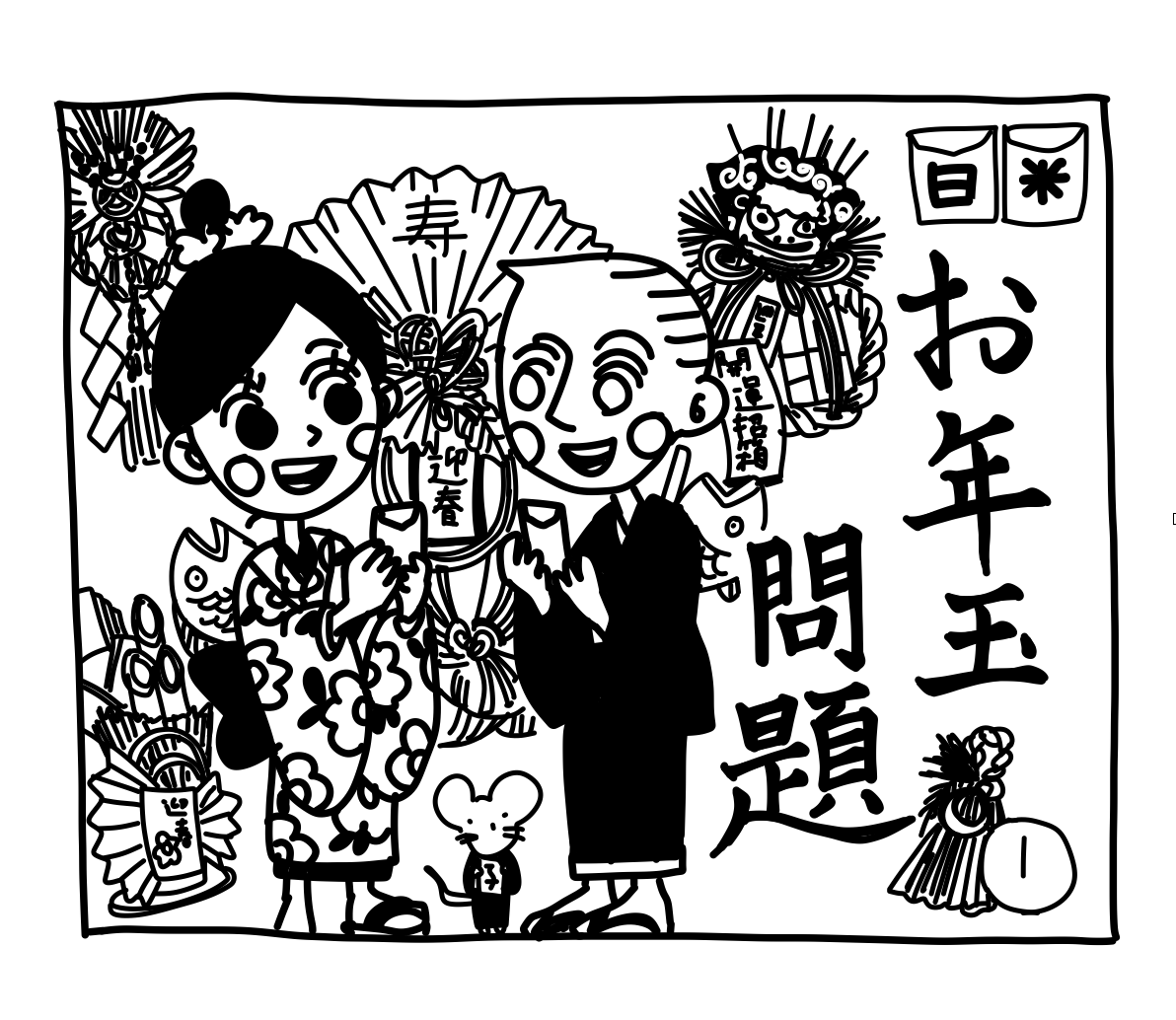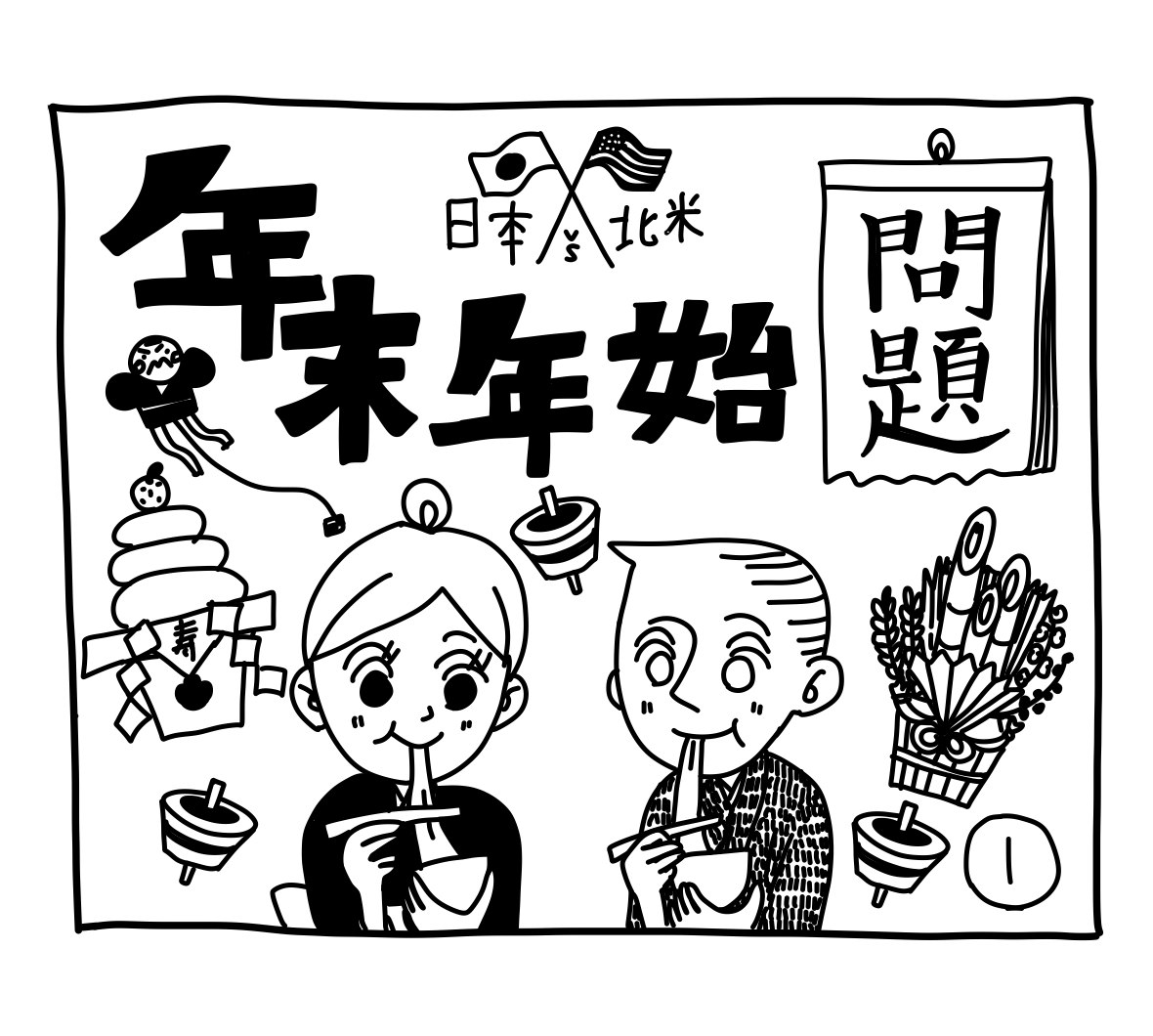©︎Travel Stock / Shutterstock.com ※画像はイメージです(以下同)
夕方にレストランの予約をしていたので、ホテル近辺を散策しようとぶらぶらしていると、すぐにまだ幼い少年が近寄ってきて片言の英語で話しかけてきた。
「ガイドは要らないか?」
よくある物乞いかなと思ったけど、とにかくヒマだったので少年の誘いに乗ることにした。

©︎Rudra Narayan Mitra / Shutterstock.com
舗装された道を一緒に歩くと、タバコ屋の店先で「タバコは要らないか?」と聞いてきたので「タバコはいいや」と断った。緑の多い街並みの中をまた少し歩くと「サリーをお土産に買わないか?安く交渉するよ」と言うので、少年の後に続いてマーケットに足を踏み入れた。
そこは旅行者向けのお土産屋さんではなく、地元の人が利用するための市場のようで、サリーを売るお店は、一枚布のサリーを地面に敷いた絨毯の上にたくさん並べていた。いや、この大量の布の中から選べと言われても! 少年は店員のオジサンに現地語で耳打ちした。それを見た途端、もしかしてここでボラれるのでは?とピリッと身構えたけど、オジサンは笑顔で「これなど如何でしょう?」と良さそうなデザインのものを何枚か見繕ってくれた。そして少年はわたしに「自分のも買ってもらってもいいか?」と聞いてきたので「いいよ」と答えると、一目散に子供服の山へと飛んでいった。
わたしは黄色地のサリーが気に入ってそれに決めた。ちょうどそこへ少年が戻って来たのだけど、手にしていた子供服はレースの袖がとてもキュートなフリフリのワンピースだった! ええ?! すすけた服を着てガイドしてくれる幼い子どもを勝手に少年だと思っていたけど、よく見たら女の子だったことに初めて気が付いた。思わずわたしは「ごめんごめん」と少女に平謝りした。そして、あんな山積みの服の中からこんなに可愛らしい服をちゃんと見つけてきたんだなと思うと密かにキュンとした。そんな私の心の内を少しも察することなく少女は「そのサリー、うちのお母さんに着せてもらったらいいよ」とさらっと提案した。

わたしはそのまま少女の家に招かれることになった。えーと、これは大丈夫なんだろうか? との警戒心はどうしても拭えなかったが、好奇心の方が勝ってしまった。サリーも子供服も安心価格でぼったくられた感もないし、まぁおそらく大丈夫だろうという楽観的判断だった。
陽が傾き始めた道をしばらく歩いて行くと、少女の家が突然、目の前に現れた。それはただワイヤーネットで囲われただけの、電話ボックスをひと回り大きくしたぐらいの小屋で、舗装された道端にいきなり建っていた。内側の棚に荷物がたくさん置かれているようだが、壁はなく、外から素通しの建物だった。
促されて中に入ると、薄暗い中に赤ちゃんを抱っこした細身の女性が、わたしを見ながらにこやかな笑みで立っていた。小さな赤ちゃんはわたしに顔を近づけると、腕に頬をすりすりして精一杯のウェルカムを表現してくれた。うわ〜可愛すぎる。途中の市場で買った、袋いっぱいのビワのような果物を手土産ですと差し出すと、少女の兄らしき男の子たちの手がいくつも伸びてきて、あっという間に奪われていった。
お母さんは少女に頼まれた通り、着付けをするためにサリーの布をわたしに当て「服の上からでいいのかしら?」と手振りで聞いた。さすがに外から丸見えの家でジーンズを脱ぐわけにはいかず、このままでお願いします、と少し後ろに下がったら、なんと暗がりの地べたにもう一人赤ちゃんが転がっているではないか! うわ、踏んじゃう! そんな状況なのに、赤ちゃんは満面の笑みでわたしを見上げていた。赤ちゃんを蹴飛ばさないようにそっと体制を立て直していると、今度は棚を伝って上からやってきたお兄ちゃんに首からぶら下げていたカメラを奪われた。いたずらっ子の笑みでニヤニヤしながらシャッターを押している。正直、気が気ではなかったが、半分あきらめの境地でお母さんにサリーの着付けをしてもらった。
外に居た少女に「せっかくだからさっき買ってきたの着てみれば?」と声をかけると、本人もそのつもりだったようで、こくりとうなずくと着ていた服を脱ぎ、そこにあったホースに手をのばすと、短い腕でかろうじて届いた頭上から水をぶっかけ始めた。これが少女にとってのシャワーなのだ。石鹸もシャンプーもないけれど、新しい服を着る前にシャワーを浴びたかったのだ。その気持ちにグッときた。バスタオルなど無く、くるくると天パーが復活した髪はもちろん全身ずぶ濡れのまま、買ったばかりのワンピースに頭を通した。少し誇らしげな表情をした少女は、周りのどの子よりとびきり可愛かった。
わたしの旅行中のテキトーなTシャツとジーンズの上から着たサリーは、実際どうなっているのか鏡がないから全くわからなかった。これでいいの? と多少困惑気味のお母さんは、最後までわたしにチップの要求などはしなかった。お兄ちゃんは相変わらずニヤニヤしながら、すんなりカメラを返してくれた(残念ながらピンボケの空間しか写っていなかった)。少女は「ホテルの近くまで送るよ」と家族との別れの時をあっさり告げた。
日が暮れた道を少女は少し先を歩いて道案内をした。わたしは、少女のワンピース姿を見た子どもたちに囲まれて、自分にも買ってくれとか、マネーマネーと囃し立てられたりとか、道すがらずっと訴えられ続けた。そんなことより、ホテルに着いたらもう少女とはさよならなのだと思ったら、急に寂しくなった。そしてその時が来た。
「ホテルはすぐそこ。自分はこれ以上行けないから」と言うと、少女は踵を返して足早に去っていった。マネーマネーと言っていた子どもたちも、ある通りから先には入ってこなかった。少女はそれきり振り返ることはなかった。
終始一貫してにこりとも笑わなかった少女は、その後もワンピースを着てくれただろうか? どんな旅のエピソードより、名前さえ知らないインドの少女のことがいまだに忘れられないでいる。