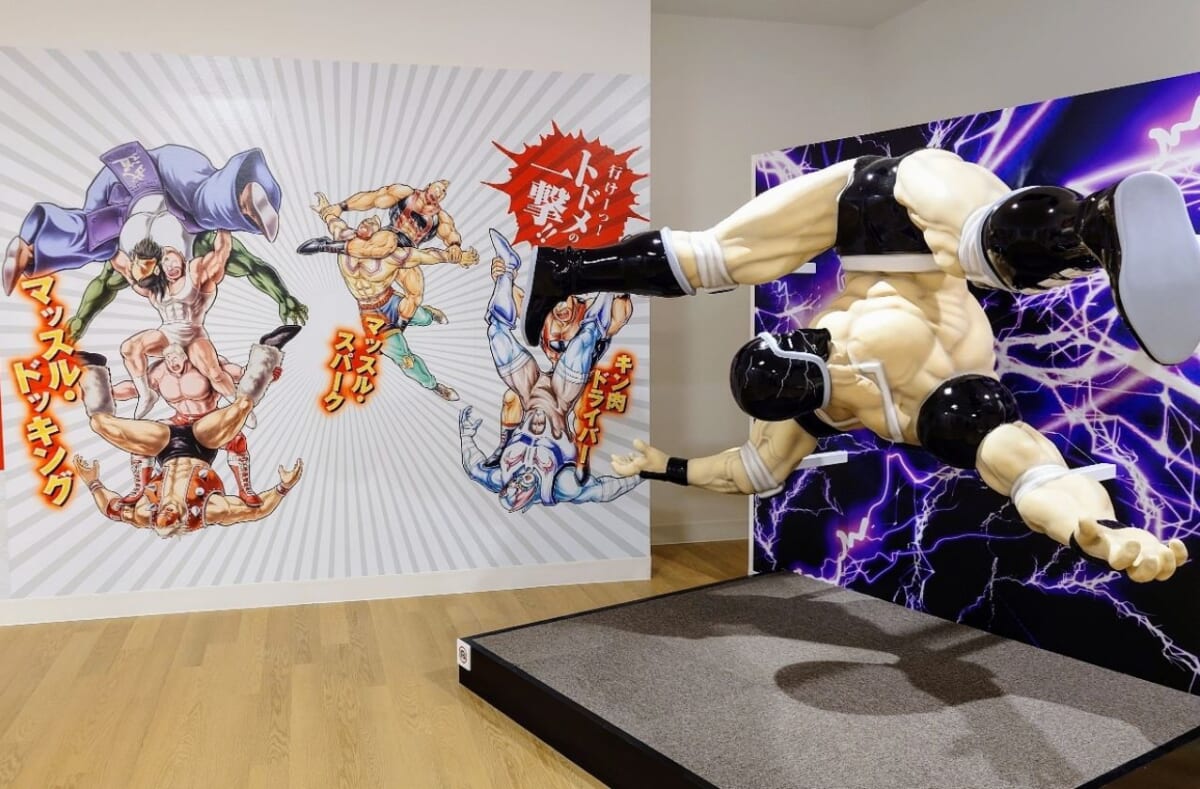静岡県が発祥!観光におすすめのスポットも
シーチキン(ツナ缶)

ツナ缶 ※画像はイメージです。
食卓でおなじみの「シーチキン(ツナ缶)」は、静岡市清水区が発祥地です。1931年、初代・後藤磯吉氏が創業した缶詰事業を受け継ぎ、1947年に2代目・後藤磯吉氏が「株式会社清水屋」(現・はごろもフーズ)を設立。1950年には社名を「後藤缶詰株式会社」に改め、マグロ油漬缶詰やミカン缶詰を輸出向けに製造・販売を行っていました。
しかし後藤氏は、輸出に頼らない自社ブランドの確立を目指し、国内市場への転換を決意。その代表格が、1958年に商標登録された「シーチキン」です。海外では原料となるビンナガマグロが「海の鶏(にわとり)」と呼ばれていることに着目し、この名前が考案されました。1967年にはテレビCMにも挑戦し、調理法の提案と合わせて広く浸透。やがて家庭の定番として不動の地位を築きました。
シーチキンについて詳しく知りたいのなら「バーチャル工場見学(※2025年7月現在は更新中)」が便利です。缶詰の発明者であるピーター・デュランドにちなんで名付けられたピーター君と、シーチキン教授と一緒に、はごろも丸に乗り、シーチキンについて学ぶことができます。ぜひチェックしてみてくださいね!
ヤマハ株式会社

ヤマハの古いオルガン
ヤマハグループは、1887年に創業者・山葉寅楠氏が浜松市の小学校で壊れた1台のオルガンを修理し、同年にオルガン製作に成功したことから始まります。1897年に日本楽器製造株式会社(現・ヤマハ株式会社)を設立し、国産初のピアノやオルガンの製造を手がけ、楽器メーカーとしての地位を確立。
戦後は音楽教室や電子楽器事業を拡大し、1983年には世界的ヒットとなるFM音源シンセサイザー「DX7」を発売しました。さらに、音響機器、ネットワーク機器、レジャー・スポーツ用品などへと事業を多角化。1955年にはオートバイ事業を分離し、ヤマハ発動機株式会社が誕生しました。以降、楽器・音響とモビリティという異なる分野で、ヤマハブランドは世界中に広がっています。
ヤマハ本社にある、完全予約制・入場無料の企業ミュージアム「YAMAHA イノベーションロード」では、ヤマハの歴史と技術を「見て・聴いて・触れて」の体験できます。約800の楽器や音響機器が展示されており、革新的製品の物語や未来技術、モノづくりのプロセスが、ヒストリーウォークで立体的に伝わってきますよ。ピアノやギターなど100点以上の現役製品を自由に試奏できるのもポイントです。
ちびまる子ちゃん

JR清水駅
「ちびまる子ちゃん」の発祥地は、静岡市清水区(旧・清水市)。ここは、原作者・さくらももこさんの故郷であり、作品の舞台となっている場所でもあります。
さくらももこさんは、静岡県立清水西高校を卒業後、静岡英和女学院短期大学(現・静岡英和学院大学短期大学部)へと進学。在学中に漫画家としての道を歩み始め、1986年には少女漫画誌「りぼん」で『ちびまる子ちゃん』の連載を開始しました。
リアルで愛らしいキャラクターたちと、共感を呼ぶ日常の描写は瞬く間に人気を博し、1990年にはアニメ化が実現。以降、ちびまる子ちゃんは国民的アニメとして、世代を超えて愛される存在となりました。
静岡市清水区にある「ちびまる子ちゃんランド」では、アニメちびまる子ちゃんのお話に登場するさまざまな場面が再現されています。さくら家の様子や、公園で遊ぶまるちゃんやたまちゃんに会うことも可能! そのほか、アニメのオープニングの世界観を体験できる「夢いっぱい」ゾーン、「まる子の夢の遊園地」ゾーンもあり、「ちびまる子ちゃん」の世界に入り込んだような気分を味わえます。
軽自動車(スズキ株式会社)

ジムニーと富士山
浜松市に本社を構えるスズキは、日本の「軽自動車」のパイオニア的存在です。そのルーツは、1909年に創業者・鈴木道雄氏が設立した「鈴木式織機製作所」。もともとは織機メーカーでしたが、戦後の復興期に「庶民にも手が届く移動手段を」との想いから、自動車産業に参入します。
1955年、スズキが初めて手がけた軽自動車「スズライト」は、日本初の本格的な量産型軽自動車として誕生。小型で低価格ながら、前輪駆動(FF)・独立懸架サスペンションなど当時としては先進的な設計を採用し、多くの人々の暮らしに移動の自由をもたらしました。
以後、スズキは軽自動車の進化を牽引し続け、「アルト」や「ワゴンR」といったヒット車を世に送り出し、1990年代以降の軽自動車市場を席巻! なお、インドでのシェアはマルチ・スズキという現地子会社を通じて、2023年度で40%以上を誇ります。
本社そばにある「スズキ歴史館」では、四輪車、二輪車、船外機といったスズキ製品はもちろん、遠州地域の物や風土なども学べます。お土産コーナーには、ここでしか手に入らないオリジナルグッズも販売しており、スズキ車好き垂涎のスポットです。
原動機付自転車

HONDA PCX
日本における原動機付自転車の礎を築いたのは、本田宗一郎氏です。1946年に浜松市中央区山下町に「本田技術研究所」を創業。陸軍が放出した無線機用小型発電機のエンジンを改良して自転車に装着した「自転車用補助エンジン(愛称:ポンポン)」の製造に成功しました。これが大きな反響を呼び、やがてホンダ初の50ccエンジン「A型」が誕生し、本格的な原動機付自転車の製造・販売がスタートしました。この一歩が、日本のモーターサイクル産業を牽引する礎石となったのです。
現在、創業地である浜松市中央区山下町にはマンションが建っていますが、歩道沿いに「ホンダ発祥の地」の説明板が設置され、当時を偲ぶことができます。また、本田宗一郎の故郷・浜松市天竜区二俣町(旧・光明村)には『本田宗一郎ものづくり伝承館』も。同氏の生涯や発明への情熱に触れられる貴重なスポットとなっています。
少年サッカー

※画像はイメージです。
少年サッカーの原点は、静岡市清水区江尻町にある江尻小学校が一つにあるとされています。かつて同校には「ボールを足で蹴ってはいけない」という校則がありましたが、子どもたちがサッカーを楽しむ姿に心を動かされた校長が、そのルールを見直し、サッカーを正式に許可したのです。
この一歩が大きな波となり、1963年には日本初の少年サッカーチームが誕生。そして1967年には、全国で初めての小学生サッカーリーグが設立されました。のちに大会出場に向け、清水市内の選抜チームが結成され、これが後の「清水エスパルス」の源流の一つとされている「清水FC」の始まりに!
現在、江尻小学校に隣接する魚町稲荷神社の境内には、サッカーボールを模した「日本少年サッカー発祥の地」碑が建立されています。清水区を訪れた際は、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。
静岡の始まりはモノづくりが主流!
静岡県は、ツナ缶やピアノ、軽自動車、原動機付自転車など、多くの“モノづくりの原点”を持つ地域です。浜松ではホンダやスズキ、ヤマハ、清水ではツナ缶「シーチキン」が誕生。モノづくりへの情熱が、時代を超えて静岡から全国、そして世界へと羽ばたいています。静岡を訪れた際は、静岡のモノづくりの原点に、ぜひ触れてみてください。
[All photos by PIXTA]