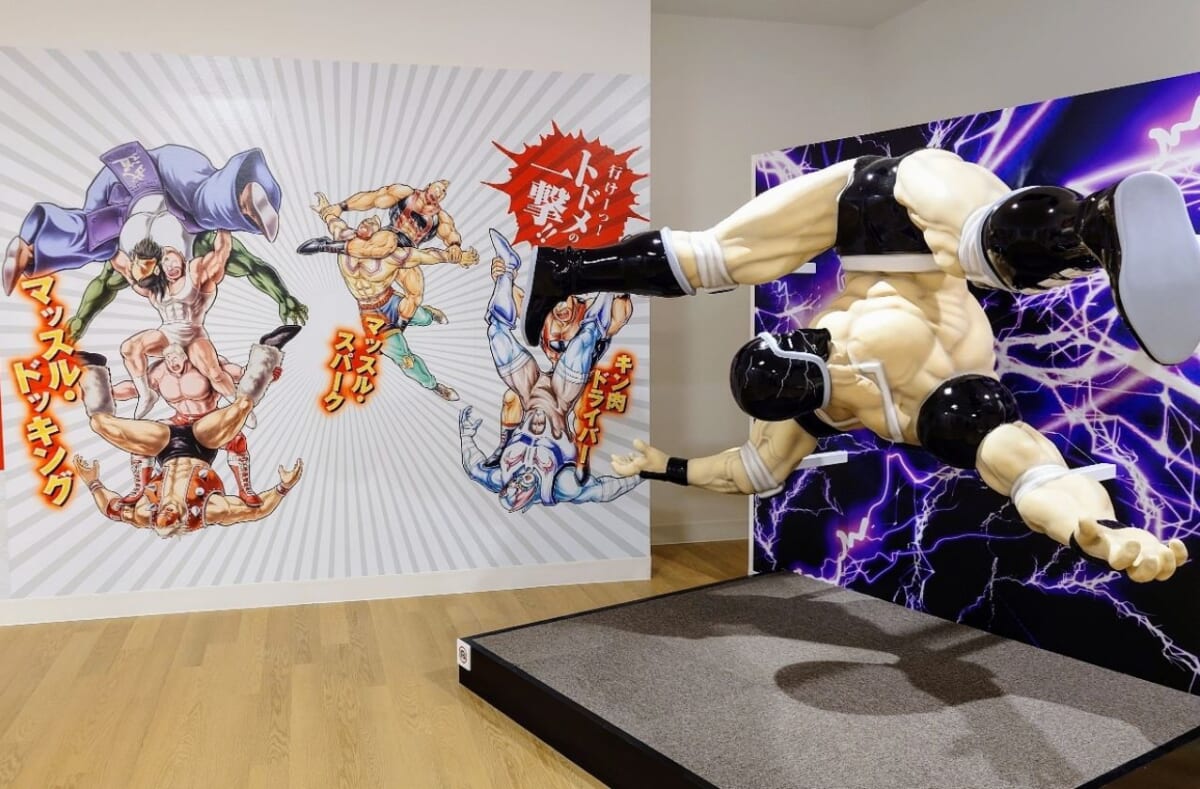田貫湖と富士山
写真提供:静岡県観光協会
7月1日は、日本の象徴かつ世界遺産である富士山の山開きです。富士山に関する記事はTABIZINEでも人気が高く、日本人に最も愛されている名峰であることが伺えます。富士登山はもはや日本人のみならず、海外旅行客にも人気。誰もが「一度は登ってみたい」と思う憧れの山なのです。
そこで、「祝!富士山開山」として、富士山のトリビアを全8回の特集でお届けします。「へえ〜、知らなかった」「なるほど、そういえば」と思う情報が満載ですので、ぜひお見逃しなく。
第7回目は、「富士山と女性の関わり」。実は富士山と女性は深い繋がりがあります。歴史を遡って、富士山との関わりを調べてみました。
江戸時代に、富士登山が大流行

(C)Matt Yamaguchi / Shutterstock.com
江戸時代には、町の至る所から富士山が見えたそうです。江戸庶民は富士山に憧れ、参詣旅行がブームに。当時は現代のように自由に旅することは出来ず、「通行手形」が必要でした。無難なのは「社寺詣で」であり、富士山登拝は通行手形を取得しやすい目的だったのです。
はじめて見る景色やご当地の美味いものを味わいながら、当時江戸から歩いて富士山を目指す旅は、途中宿泊も含めて往復合計10日間ほどもかかりました。現代でいえば、海外旅行へ行くレベルかもしれませんね。庶民にとっては、ワクワクするような憧れの旅だったのでしょう。

提供:富士宮市
富士講ってなに?
富士山は「講(こう)」というグループのメンバーとなって登るのが一般的でした。富士山の信心者によって構成された組織が「富士講」。登山者は「山役銭(やまやくせん)」という入山料をはじめとする10日間の旅行費用(宿泊代や飲食費)を「講」で積み立てたのです。
富士講本部は渋谷の道玄坂にあった

渋谷の大地主で、江戸最大の富士講「山吉講」の吉田家は、道玄坂109の裏手にありました。山吉講が「御水さん」「御水講」と呼ばれるのは、親が富士山頂で「金名水」を発見したからだと言われています。
女人禁制だった富士山

現在では世界中から「山ガール」が集まる富士山ですが、昔は女性は入山出来ませんでした。富士山に限らず、比叡山や高野山など霊山、相撲の土俵や酒造も女人禁制でした。
富士山は「女性の入峰(富士山に入る)は修行の妨げとなる」とされ、入山が許されたのは2合目の御室浅間神社まで。庚申(かのえさる)の年、麓で7日間の修行をした者だけが4合5勺の御座石浅間神社まで登ることができたそうです。一般的に女性の登山が解禁されたのは、1872(明治5)年3月のことでした。
富士山に行けない女性はどうしたの?
富士山参詣に行けない女性は、富士山の代わりに「富士塚」に登りました。富士塚とは富士山のミニチュア。富士山参詣に行けない女性や老人・子供のために作ったもので、富士山に登る代わりに富士塚に登り、富士山を信心したそうです。関東各地に「富士塚」があります。女性も含めて、富士山に行きたい思いを抱いていた人が多かったのでしょう。
都指定有形民俗文化財(指定:昭和56年3月12日)になっている、千駄ヶ谷の鳩森八幡神社の富士塚。富士山を模した「富士塚」が残っています。実際に登ることも出来ますよ。
住所:〒151-0051東京都渋谷区千駄ケ谷1-1-24
電話:03-3401-1284
公式サイト:http://www.hatonomori-shrine.or.jp/
はじめて富士山に登った女性は
1832年(天保3年)高山たつが日本人女性で初めて登頂、「どうしても富士山に登りたい」という気持ちから、髪を切り男の姿に身を変え富士山に入りました。ただし、「富士講」の構成員であり、登頂の際は男性に混じって登山したようです。
外国人では、1867年にイギリスの行使パークス夫人が登っています。
実は紀元前にすでに登頂した人物がいた
紀元前に木花咲耶姫(このはなさくやひめ)が、富士山に登頂しているとされています。「姫」と名のつく通り、女性ですね。そう、神話の世界で富士山の初登頂は、女性だったと記されているのです。
ドラマティックな木花咲耶姫の人生
木花咲耶姫(このはなさくやひめ)は、儚い花のように美しく、桜(さくら)は彼女の名前から名付けられたと言われています。
天照大御神(あまてらすおおみかみ)の孫、天津日高日子番能邇邇芸命(あまつひこひこほのににぎのみこと)が下界に降りた時、笠沙の岬(鹿児島県)の浜辺を歩いている姫を見つけ、稀に見る美しさに一目惚れしました。木花咲耶姫(このはなさくやひめ)の父神大山津見(山の神)は喜んで結婚を許し、たくさんの結納品と共に、木花咲耶姫の姉の磐長姫(いわながひめ)も一緒に差し上げました。当時は姉妹が一緒にひとりの男性に嫁ぐ、姉妹婚はよく行われていたそうです。ところが、姉の磐長姫は岩のようながっしりとした身体つきに、醜い顔をしていたので、「姉は不要」と実家に返されてしまいました。
その後、木花咲耶姫(このはなさくやひめ)は目出度く懐妊しました。結婚して1日しか一緒に過ごしていない夫の邇邇芸命(ににぎのみこと)は、たった一夜で身籠もったのはおかしいと疑います。言いがかりをつけられた姫は疑いを晴らすため、「天照大御神(あまてらすおおみかみ)の孫の邇邇芸命の実子であれば、どんな状況でも無事生まれる」と宣言。出入口も隙間もない産屋に火を放ち、燃え盛る火中で火照命(海彦)、火須勢理命、火遠理命(山彦)の3人の男児を出産しました。
火中で無事出産したことにより、実父であり山の神である大山津見に、日本一の「富士山」を譲(ゆず)られたと言われています。当時の富士山は噴火を繰り返して、火を吹き、「怒れる火の山」でした。ところが、火を恐れない木花咲耶姫(このはなさくやひめ)が富士山に登り、山頂に近づくにつれ、富士山の地鳴りは静かになり、吹き上げていた火は鎮火しました。富士山を鎮めた結末には諸説あり、木花咲耶姫(このはなさくやひめ)が富士山の火口に身を投げて、富士山を鎮めたとも言われます。
富士山の神様は女性

曇海に浮かべる富士山
写真提供:静岡県観光協会
富士山を鎮めた木花咲耶姫(このはなさくやひめ)が、富士山の神さまです。火中出産の神話により、ご利益は「安産」「火防」「水を司る神」の信仰を集めています。
住所:〒418-0067 静岡県 富士宮市 宮町1番1号
公式サイト:http://www.fuji-hongu.or.jp/sengen/index.html
一方、姉の磐長姫(いわながひめ)は出戻りの我が身を恥じ、身を隠していたようですが、京都の貴船神社の中宮・結社(ゆいのやしろ)で、御祭神として祀られています。縁結びの神さまですが、貴船神社は「丑の刻参り」ゆかりの地でもあります。
富士山は女性と縁が深い山だった
女人禁制であった富士山は、実は女神が御祭神であり、女性と関わりが深いことが分かりました。しかも、かなり人間的なエピソードがあり、身近に感じますね。女人禁制であったことには、「自分より美しい女性を見ると、山の神が嫉妬して荒れるので、山に女性を入れてはいけない(再び噴火が起こる可能性を怖れる)。」という説もあります。絶世の美女で、噴火を鎮めるほどパワーがある女神であっても、いつの世も女心は変わらないのでしょうか。
ともあれ、日本の名峰富士山は、女神に守られています。私たちが富士山に惹かれるのも、富士山に母性を感じるからかもしれませんね。
「【特集】あなたの知らない富士山トリビア〜今年も富士山登山の季節到来!〜」もお見逃しなく!
[富士山のふしぎ100|偕成社]
[富士山のすごいひみつ100|主婦と生活社]
[富士山NET 女人禁制時代に女性が富士山を遥拝した場所とは?]
[NHK 歴史秘話ヒストリア エピソード2 富士山に登りたい~女人禁制に挑んだ女性の苦闘]
[富士山本宮浅間大社 御由緒]
[一般社団法人富士五湖観光連盟 富士山巡礼の旅 ]
[Fujigoko.TV. 富士山噴火史 ]
[横浜歴史研究会 高尾 隆「江戸庶民の憧れ―富士講」]
[かくたに 木花咲耶姫 富士宮に伝わる昔のおはなし]
[図解ひとり登山 富士山の神様〜木花咲耶姫(6/6)そして神へ]
[貴船神社 由緒]
[オールカラーでわかりやすい!古事記・日本書記|西東社]
[Photos by shutterstock.com]