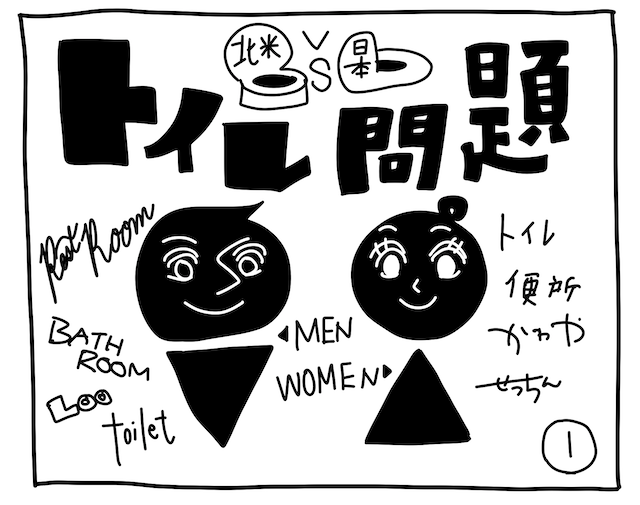売上高で見れば日本が世界一

海外旅行に出かけると、空港などで珍しい自動販売機を見かけます。しかし、街中を歩いている時には、なかなか目に留まらない気もしますが、いかがでしょうか?
日本の街を歩けば、都市部も田舎も関係なく、自動販売機を見かけます。中には食べ物やアイスクリームの「自販機」もありますよね。
この自動販売機、日本自動販売システム機械工業会の資料によれば近年数を大幅に減らしているみたいですが、世界で2番目に多い約400万台が国内には存在するそう。
海外のウェブサイト『BRANDONGAILLE』によれば、464万台近くが稼働するアメリカが、台数こそ世界一だといいます。しかし、売上高で比べれば、日本は年間約5兆円(うち飲料は約2兆円)で、アメリカを1兆円ほど上回っており、日本が世界一になると全国清涼飲料連合会の情報にもあります。
さらに、3億3,000万人ほどいるアメリカ人と1億2,000万人ほどの日本人、人口一人当たりの自動販売機の数では日本が勝っています。日本の外務省によれば、アメリカの国土は日本の約25倍です。
国土の狭い日本にアメリカと同程度の自動販売機が存在するのですから、街の至るところに設置されている印象を日本では受けるのですね。
ホット&コールドの自動販売機は日本で誕生

ところで、この自動販売機、そもそもいつごろから地球上に存在するのでしょうか?その歴史は意外に古く、全国清涼飲料連合会によれば、紀元前1世紀のエジプトにまでさかのぼれるのだとか。コインを入れると、その重みで聖水が出てくる機械が自動販売機の源流といわれています。
産業革命後のイギリスでは、飲料・菓子・食品・チケット・たばこなどの自動販売機が実用化され、戦後にアメリカの飲料が日本に流入・普及するとともに、治安の良さも手伝って、いよいよ日本で「自販機」の数が増えていったそう。1960年代に100円玉が大量に流通すると、国内の自動販売機はさらに増え、1974年には温かい飲料と冷たい飲料が同時に販売できる「ホット&コールド機」が日本で誕生します。

上述のウェブサイト『BRANDONGAILLE』にも自動販売機の世界史が詳しく書かれています。
- 1700年代・・・コイン式のたばこの自動販売機がイギリスで誕生
- 1880年・・・ポストカードを売る自動販売機がロンドンで誕生
- 1905年・・・アメリカで切手の自動販売機販売が始まる
- 1937年・・・瓶入りのコカ・コーラが自動販売機で売られ始める
- 1961年・・・缶入りのソフトドリンクが自動販売機で売られ始める
- 1972年・・・お菓子を売るガラス張りの自動販売機が誕生する
- 1987年・・・アイスクリームの自動販売機が発明される
これらの世界史の中で日本独自の歴史が展開し、今では売上高が世界で一番になるくらい自動販売機が普及したのですね。

以上が世界一を誇る日本の自動販売機の世界になります。とはいえ、最近ではコンビニエンスストアなどの台頭で、かなり苦戦しているようです。その台数は過去10年で100万台以上も減少しています。
東日本大震災の直後は、夏の電力ピーク時に発生する電力消費が問題視された時期もありました。なかなか苦境に立たされているみたいですが、それでも世界一の売り上げを誇る日本の自動販売機業界。
まだまだ存在意義はあるはずです。この夏は、自動販売機で水分補給のために積極的にドリンクを購入し、世界一の売り上げを誇る日本の「自販機」の豊かさを実感してみてはいかがですか?
[参考]
※ 普及台数 – 日本自動販売システム機械工業会
※ 25 Intriguing Vending Machine Sales Statistics – BRANDONGAILLE
※ 自販機の歴史 – 全国清涼飲料連合会
※ Vending Machine Operators in the US – IBISWorld
※ アメリカ合衆国(United States of America)基礎データ – 外務省
[All photos by Shutterstock.com]