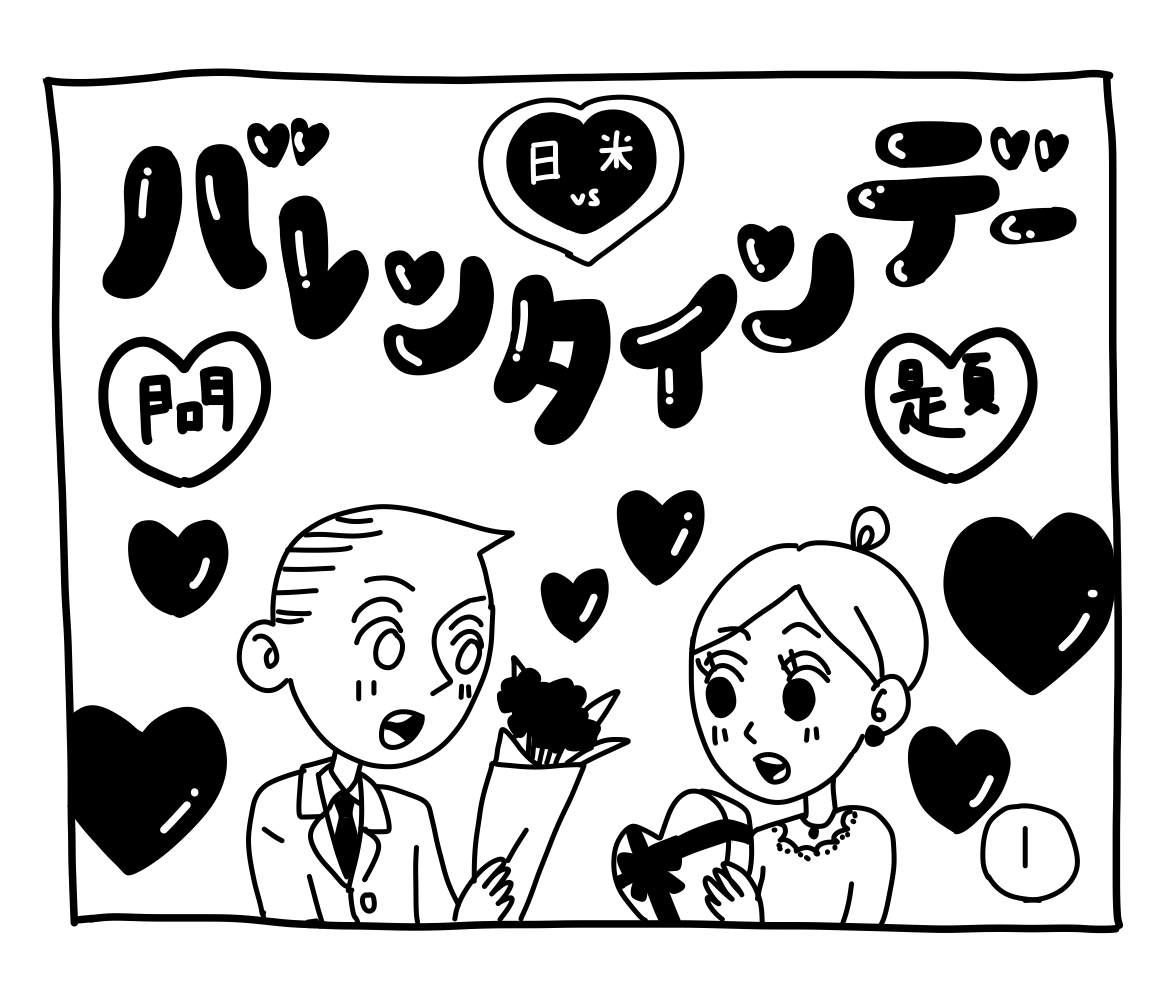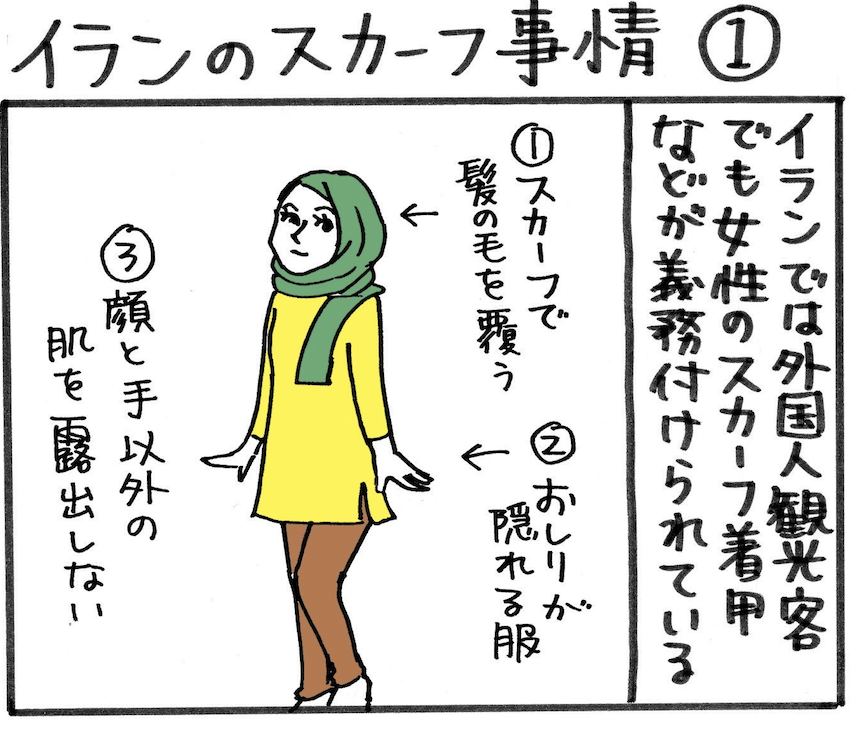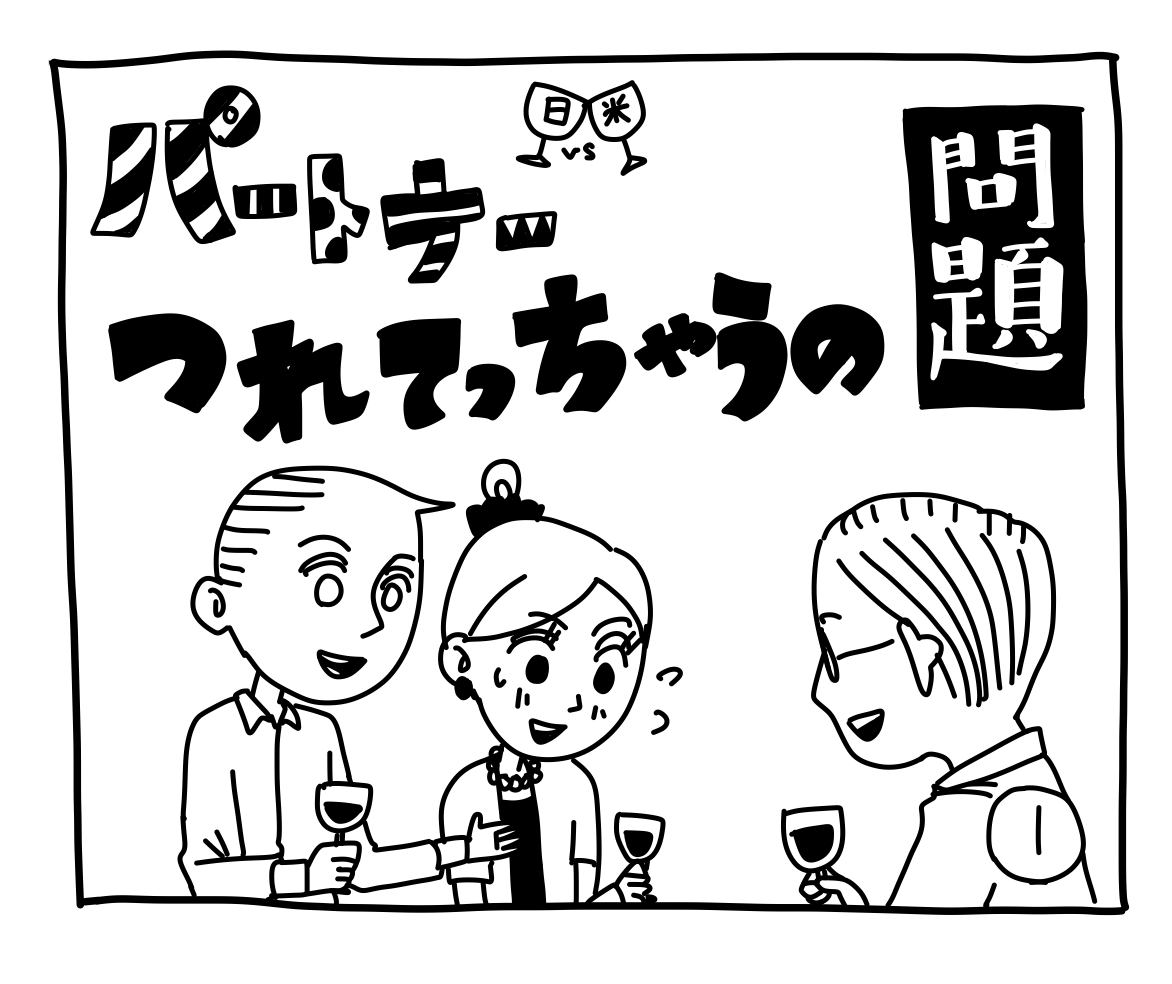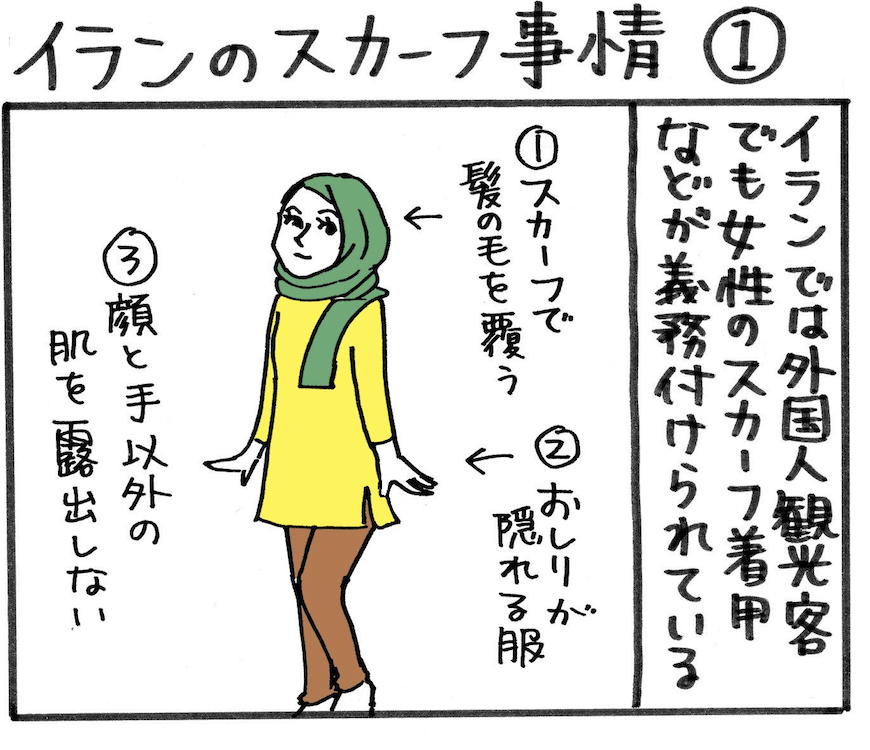北海道・東北エリア
北海道:倶知安(くっちゃん)
青森県:撫牛子(ないじょうし)
岩手県:千厩(せんまや)
宮城県:愛子(あやし)
秋田県:男鹿(おが)
山形県:左沢(あてらざわ)
福島県:勿来(なこそ)

倶知安駅
北海道・東北エリアで選出されたのは上記。北海道の「倶知安(くっちゃん)」は、アイヌ語の「クッシャニ」に由来し、それが転訛して「クッチャン」となり、さらに漢字があてられて現在の表記になったとされています。青森県の「撫牛子(ないじょうし)」にもアイヌ語起源という説があるものの、語源ははっきりしていません。岩手県の「千厩(せんまや)」は、平安時代に奥州藤原氏がこの地に厩(うまや)を建て、千頭もの馬を飼育していたことに由来しています。

勿来関跡
宮城県の「愛子(あやし)」は、一見すると人名のようですが、古くから地元で信仰されている「子愛(こあやし)観音堂」の文字を入れ替えて、名付けられたのだとか。福島県の「勿来(なこそ)」は、いわき市南部に位置し、かつての国境「勿来関(なこそのせき)」に由来すると伝えられています。
関東エリア
茨城県:行方(なめがた)
栃木県:神鳥谷(ひととのや)
群馬県:六合(くに)
埼玉県:越生(おごせ)
千葉県:匝瑳(そうさ)
東京都:舎人(とねり)
神奈川県:弘明寺(ぐみょうじ)

行方市の風景
関東エリアで選ばれたのはこれらの地名たち。茨城県の「行方(なめがた)」は、思わず「ゆくえ」と読んでしまいそうですが、ヤマトタケルノミコトがこの地の水辺と台地が入り組んだ風景を「行細し(なめくわし)」と表現したことが名前の由来とされています。群馬県の「六合(くに)」は、1900年に当時の草津村から分村される際、六つの集落が合わさってできたことからその名がつけられました。

越生駅周辺の町並み
埼玉県の「越生(おごせ)」は、難読地名としても有名です。秩父方面にも上州方面にも、町から出るには尾根や峠を越えなければならなかったことから、「尾根越し(おねごし)」となり、それが「尾越し(おごし)」と転じたのが語源とされる説が有力。東京都足立区の「舎人(とねり)」という地名の由来は諸説ありますが、聖徳太子が身分を隠して関東を巡行していたとき、ただ一人、その正体を見破った舎人にちなんで命名されたという伝承があります。
北陸・甲信越エリア
新潟県:新発田(しばた)
富山県:石動(いするぎ)
石川県:羽咋(はくい)
福井県:敦賀(つるが)
山梨県:百々(どうどう)
長野県:麻績(おみ)

敦賀市にある水島
北陸・甲信越エリアで選出された地名は、どれも一癖あり! 見たことはあっても、正しく読めない地名ばかりです。新潟県の「新発田(しばた)」は、その由来に諸説ありますが、有力なのは、この地域がかつて海岸近くの州だったことから「州端(すばた)」と呼ばれ、それが転じて「新発田(しばた)」になったという説。福井県の「敦賀(つるが)」は、敦賀半島が角(つの)ような形をしていることから、「角処(つのか)」と呼ばれるようになり、やがてそれが変化して「敦賀(つるが)」になったという説などがあります。

※画像はイメージです。
山梨県南アルプス市の「百々(どうどう)」という地名はユニーク。この地名は、急流の音が響く様子を表していると考えられているそうです。水音を「どうどう」と表現し、水音が繰り返すさまを表すために「百(ひゃく)」という文字が使われているのだとか。
東海エリア
岐阜県:尻毛(しっけ)
静岡県:函南(かんなみ)
愛知県:御器所(ごきそ)
三重県:駅部田(まえのへた)

函南の十国峠
東海エリアにも読みづらい地名がずらり。岐阜県の「尻毛(しっけ)」は、「湿気(しけ)」が転じたとする説があります。静岡県の「函南(かんなみ)」は、箱根(函嶺)の南に位置していることに由来。

地下鉄「御器所駅」
名古屋市昭和区の「御器所(ごきそ)」は、かつてこの地で熱田神宮に供える「御器(土器)」を製造していたことから名付けられたといわれます。一方、三重県の「駅部田(まえのへた)」は、現在の「前野ヘタ町」にあたりますが、その語源については諸説あるものの、詳しいことは分かっていません。
近畿エリア
滋賀県:膳所(ぜぜ)
京都府:間人(たいざ)
大阪府:放出(はなてん)
兵庫県:宍粟(しそう)
奈良県:京終(きょうばて)
和歌山県:六十谷(むそた)

膳所城跡公園
近畿エリアで選出された地名も難解! 滋賀県大津市の「膳所(ぜぜ)」は、平安時代に天皇の食事の準備をする場所(御厨)として指定されていたことに由来。京都府の「間人(たいざ)」は、現在の京都府京丹後市丹後町に位置し、聖徳太子の母である間人皇后がこの地に身を寄せた際、村人たちの温かいもてなしに報いるため、自身の名前をこの地に贈ったと伝わります。

大阪府の「放出(はなてん)」は、この地がかつて岬のように突出していた、水を流す樋門(ひもん)を設けていた、新羅の道行という僧侶が、この地で暴風雨に遭い、それを神罰だと思って、草薙の剣を河の中に放り投げたといったさまざまな説があります。奈良県の「京終(きょうばて)」は、平城京の南東端に位置することから「都のはて=京終」と名付けられたそうです。
中国・四国エリア
鳥取県:皆生(かいけ)
島根県:十六島(うっぷるい)
岡山県:美作(みまさか)
広島県:三次(みよし)
山口県:特牛(こっとい)
徳島県:府中(こう)
香川県:栗林(りつりん)
愛媛県:松前(まさき)
高知県:宿毛(すくも)

皆生温泉
中国・四国エリアで選出された地名はこちら。鳥取県の「皆生(かいけ)」は、もとはこの地にあった「海池」と呼ばれる大きな池があり、1867年に「海池」が「皆生」になったのだとか。広島県の「三次(みよし)」は、「水(み)」と古代朝鮮語の「村(すき)」が合わさって「水村(みすき)」となり、それが「みよし」に変化したという説が有名です。

高知県宿毛市の景色
徳島県の「府中(こう)」は、かつて「ふちゅう」と読まれていましたが、「不忠」に通じるとして、「孝(こう)」に改められたといいます。高知県の「宿毛(すくも)」は、古代、この地域が葦が生い茂る湿地帯で、その枯れた葦を「スクモ」と呼んだことに由来するそうです。
九州・沖縄エリア
福岡県:雑餉隈(ざっしょのくま)
佐賀県:厳木(きゅうらぎ)
長崎県:女の都(めのと)
熊本県:八景水谷(はけのみや)
大分県:安心院(あじむ)
宮崎県:都城(みやこのじょう)
鹿児島県:指宿(いぶすき)
沖縄県:保栄茂(びん)

西鉄「雑餉隈駅
九州・沖縄エリアも、難読の宝庫。福岡県の「雑餉隈(ざっしょのくま)」は、大宰府の役人「雑掌(ざっしょう)」が住んでいた地という説が有力。佐賀県の「厳木(きゅうらぎ)」は、大きなクスノキが川を越えて倒れた伝説があり、その威厳から「厳木」と呼ばれるようになったとか。

宮城県の「都城(みやこのじょう)」は、室町時代に2代目・北郷義久(よしひさ)が都島に築いた城「都之城」に由来。鹿児島県の「指宿(いぶすき)」の語源は「湯生村(ゆふすきむら)」で、それが長い歴史の中でイフスキ、そしてイブスキへと変化していったと考えられています。沖縄県の「保栄茂(びん)」は、沖縄(琉球語)の二重母音によって、かつて呼ばれていた「ぼえも」が「びん」となり、それを漢字で表記したものだそうです。
[参考]
ソニー生命「47都道府県別 生活意識調査2024」
[All photos by PIXTA]