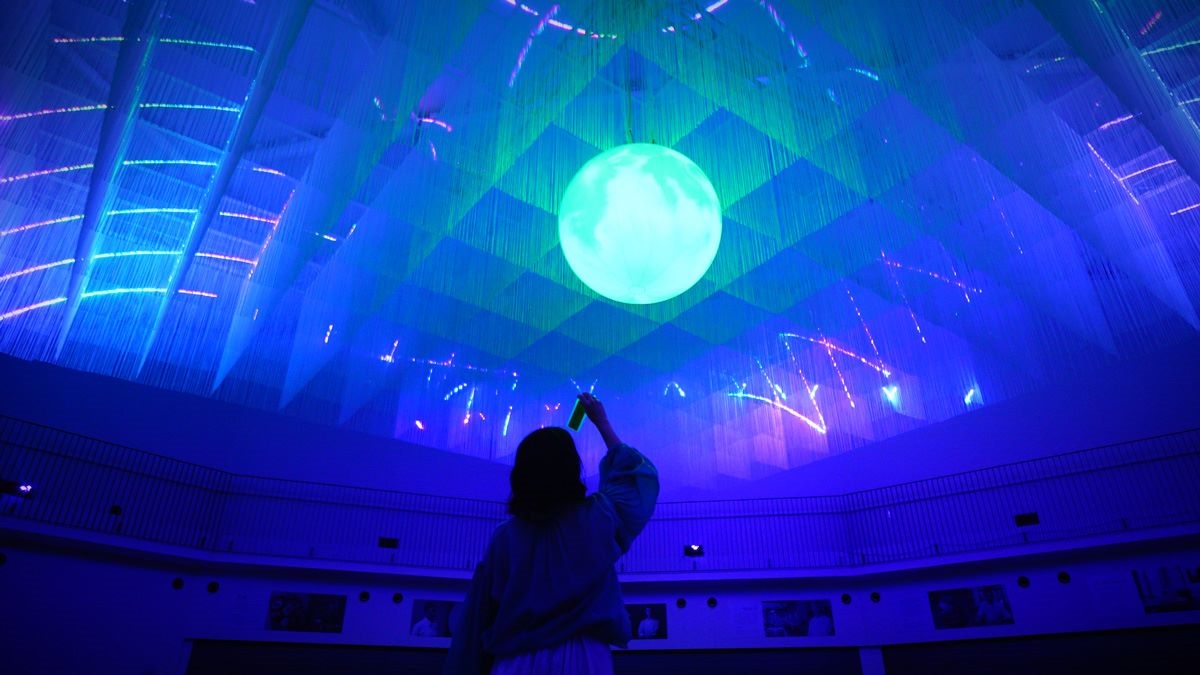紀州犬
日本には世界に例を見ないユニークな文化や歴史があります。外国人から「面白い!」「不思議」と興味を持たれるものも多いです。今回ご紹介する「おかげ犬」もそのひとつかもしれません。おかげ犬とは一体どんな犬なのでしょうか?
「おかげ犬」とは?

伊勢神宮内宮
江戸時代の日本では「おかげ参り」のブームが巻き起こりました。おかげ参りとは、群衆による伊勢神宮参拝のこと。江戸時代はずっと伊勢参りが流行していましたが、約60年周期(江戸時代で3回)で大ブームとなり、日本全国から集団で伊勢神宮を参詣したそうです。
しかし、体が弱いなどの事情があって、伊勢神宮に参詣できない人もいました。そのご主人の代わりに伊勢神宮を参詣と言われているのが「おかげ犬」なんです。近所でおかげ参りに行く人に一緒に連れて行ってもらっていました。しかし、そのうち犬だけで自宅と伊勢神宮を往復するケースも出てきたそうで、ビックリですよね!
犬のおかげ参りの仕方

(画像はイメージです)
犬がご主人の代わりにどのように伊勢神宮を参詣したのでしょうか? 気になりますよね。誰からも代参だとわかるように、犬に道中でかかるお金や伊勢参りをする旨を書いたものをしめ縄でつけていたとのこと。
不思議なことに、誰も犬のお金を奪うようなことはしなかったそうです。むしろ犬をリレー式で伊勢神宮に連れて行ったり、エサや寝床を与えたりして、積極的にサポートしていました。当時の人たちは、そうすることで、徳を積めると考えていたそう。江戸時代の人たちは信仰心が厚く、温かい心を持っていたんですね。
そして、伊勢神宮にたどり着いた犬は伊勢神宮の神官から竹筒に入ったお礼をもらい、ご主人の元に帰りました。江戸時代に何頭の犬が伊勢神宮を代参したかはわかりませんが、歌川広重「伊勢参宮 宮川の渡し」や「東海道五十三次 四日市」にもおかげ犬が描かれていますので、結構な数の犬が代参していたようです。
代参犬として有名なシロの伝説

秋田犬
福島県須賀川の十念寺には代参をしたと言われている「シロ」にまつわる犬塚があります。須賀川の旧家・市原家に飼われていたシロは利口だと町中からも評判だったそう。しかし、ある年にご主人が病に倒れ、毎年恒例の伊勢参りができない状態になってしまいました。そこでシロが代参することになります。道中、人々の助けを借りつつ、伊勢神宮を果たしたシロ。2か月後には無事に家に戻ってきたとのこと。
江戸から伊勢まで人の足でも片道15日かかったそうですから、シロにとっては大冒険の旅
だったに違いありません。シロが旅の途中どのような光景を目にし、どんな旅人たちに出会ったのか・・・想像すると不思議な気持ちになってきます。
江戸時代の人たちの情熱がすごい! 「抜け参り」とは?

伊勢神宮内宮
飼い主の代わりに伊勢神宮を参拝していた犬がいたことにも驚きましたが、江戸時代には家族に黙って参拝に出かけてしまう人までいたそうです。それを「抜け参り」と言います。子どもが親に黙って、抜け参りすることもあったとか! 信じられないことに、抜け参りは容認されていて、抜け参りをした人を誰も責めることができなかったと言います。当時は伊勢神宮を参拝することが善業という風潮だったんですね。
「一生に一度はお伊勢さん」と言われるほど、江戸時代に生きた人たちにとって伊勢神宮は憧れの存在でした。そのため、誰にも内緒で伊勢を目指して旅をする人もたくさんいたのでしょう。
犬の代参はいつ終わったのか?
江戸時代の人々と犬との温かな関係は、明治維新後に終わってしまいます。それまでいたるところに住み着き自由に暮らしてきた犬たちですが「畜犬規則」によって、飼い主のいる犬といない犬が分けられ、いない犬は駆除されてしまったのです。また、欧米人によって持ち込まれた西洋犬を飼う日本人も増えたとか。それらの影響で、日本型の里犬(秋田犬やチンなど)の数も一時的にかなり減ってしまったそう。
明治維新で江戸時代の文化のひとつ「おかげ犬」が失われたのは、非常に残念だと思いました。もし今もなお、おかげ犬の文化が続いていたら、日本が世界に誇れる文化になっていたかもしれませんね。車などが走っていて、危険なので、難しいでしょうけど・・・。江戸時代を生き、代参した忠犬たちに思いを馳せずにはいられません。
なお、今でも伊勢神宮のお土産として「おかげ横丁」などでおかげ犬のグッズを購入することができますよ。伊勢神宮を参拝する際、ぜひチェックしてみてくださいね。
参考
[犬の伊勢参り]
[おかげ横丁のおかげ犬]
[環境省]
[All photos by Shutterstock.com]