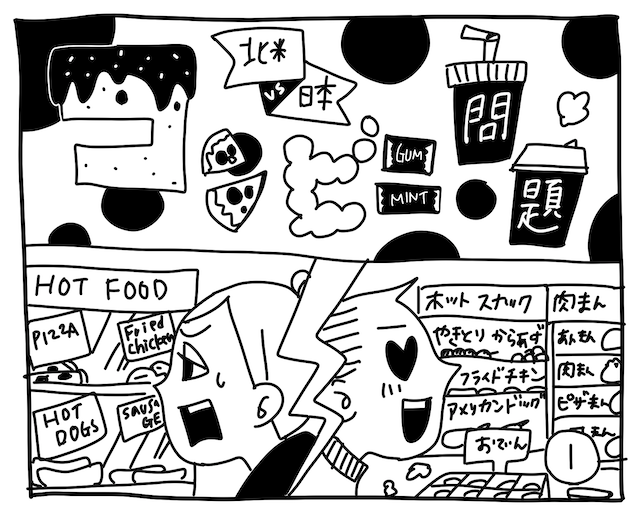フライト中にうまく眠れるかが乗客の課題だったりしますが、安全な飛行という前提があってこそ。もし、その機体を守っているパイロットも眠っていると知ったら、あなたは熟睡できますか?いくら自動操縦中だとしても、恐怖を感じますよね。
機長も副操縦士も同時に居眠り!?

英国航空パイロット協会が500人を対象とした調査において、43%がコックピットで居眠りしたことがあると回答しました。2012年と少し前の情報ですが、英紙テレグラフの記事に掲載されました。
また2013年には、同協会の調査で56%が居眠り経験ありという記事が出ています(英紙ザ・サン)。さらに、そのうち29%は、目覚めたとき副操縦士も居眠りしているのを目撃したことがあるという、衝撃のデータが明らかになりました。
45%が深刻な疲労を感じていて、20%が週に1回以上妥協のパフォーマンスをしているという調査結果もあります(英紙デイリーメール)。
パイロットは長時間労働で過酷な職業と知っていても、ベストパフォーマンスで運航されていない可能性があると思うと乗客は複雑です。社会人なら、いつでも最高のパフォーマンスが出せるものではないと経験から分かっているのですが、やっつけのフライトは想像したくありません。
世界中で起きているパイロットの居眠り事件簿

パイロットの居眠りにより、これまでに起きた事件をいくつかご紹介しましょう。
今年、オーストラリアでは、貨物機のパイロットが居眠りのため、到着予定地のキング島を46km通り過ぎていたことがありました。パイロットは1人だけで、どれくらい寝ていたのかは不明です。管制塔が、連絡が取れないことに気づき、発覚しました。このパイロットは休暇明けで、1本目のフライトだったそう。
旅客機でも同様のことが起きています。2008年のエア・インディアでは、ドバイ発の機体が到着予定地のムンバイを通過。機長と副操縦士の両方が居眠りをしていました。徹夜でのフライトだったそうです。管制塔が、操縦室の警告音を鳴らして二人は目を覚ました。普段なら空港の約160km手前で下降をし始めるところ、高度も速度も一定のまま通過し、管制塔からの指示は無視。管制塔ではハイジャックの可能性も考えていたそうです。

2017年には、タイガーエア・台湾で、副操縦士が機長の居眠りの写真を撮り、その画像を流出させるということが起こりました。同社では居眠りは禁じられていましたが、機長を起こすことなく1年間写真を撮りためていた副操縦士は懲戒処分となりました。ちなみに同社は、操縦士の月間平均飛行時間は約70時間から80時間であり、台湾の航空当局が定めた月120時間の上限に達していないので、そこまでの負荷はかけていなかったと主張しています。
ほとんどが事なきを得ていますが、1時間睡眠でフライトに臨んだパイロットによる墜落事故などもあります。
乗客としては、大勢の命を預かるパイロットの環境づくりは急いでしてもらいたいものです。
※写真はすべてイメージです。
空港、飛行機関係のトリビアについては、『【特集】元空港グランドスタッフの、今だから話せる驚きの実話』『マニアの間で人気!?三角マークがついている飛行機の座席の意味とは?』などもぜひチェックを!
参考
[Nearly half UK pilots have fallen asleep in cockpit, MPs told|The Telegraph]
[Half of pilots fall asleep on job|THE Sun]
[Revealed: Packed passenger plane was left flying on autopilot after BOTH pilots fell asleep in the cockpit|Mail Online]
[パイロットが居眠り操縦、目的地通り過ぎる オーストラリア|CNN]
[機長と副操縦士がともに居眠り、到着空港を通り過ぎる エア・インディア|AFP]
[タイガーエア・台湾、パイロット居眠り報道に見解 「過大な負担かかる乗務はなかった」|Traicy]