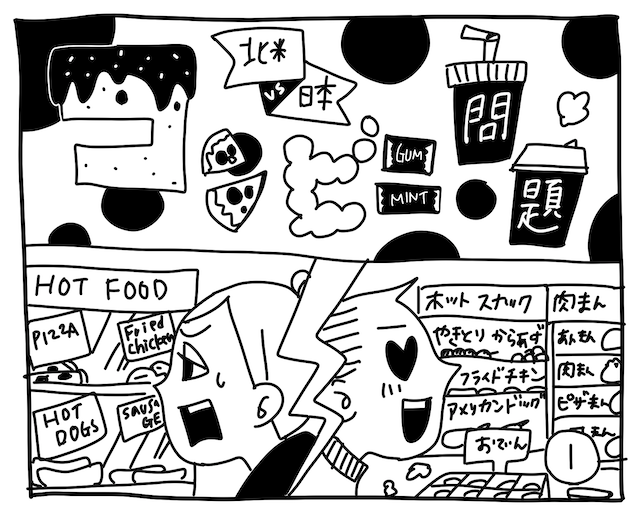飛行機の窓といえば、角が丸くなった小さな窓ですよね。どうして建物の窓のように四角く角張っていないのでしょう?なぜ小さいのでしょうか?また、その窓には小さな穴が開いていますが、いったい何のためなのでしょう?これらの理由を調べてみました。
最初は飛行機の窓は四角だった!

今使われている飛行機の窓は、すべて角丸や楕円になっています。
もともとは違っていて、四角い窓が使われていました。たとえば、1949年に記念すべき初フライトを飾った、世界初の商業旅客機デ・ハビランド コメット。角張った四角い窓が使われていました。
1954年のこと。2件の致命的な墜落事故が起きます。それは、機体の構造的な弱点によるものと判明。四角い窓の隅に危険なストレスがかかっていたことにより、構造が弱くなっていました。窓枠は、他の部品の2~3倍もの圧力を受けて、金属疲労を起こしていたのです。
設計の変更を受け、今のような角が丸くなった窓が使われるようになりました。1950年代後半のことです。
客室の窓は三重構造

さて、飛行機の客室の窓は、ガラスより軽いアクリルでできていて、三層構造になっています。窓の厚みは、外側が9mm、中央が6mmといったものです。
機内では、薄くなった気圧を地上のものに近づけるために与圧をしています。これにより、窓部分にも大きな負荷がかかります。1枚でも与圧に耐えるよう設計されていますが、念のため、3枚入れています。
また、与圧は機体全体に負荷をかけます。それに耐えるために機体にはたくさんの柱が入っています。柱の間に窓を設けているため、また窓を軽く保つために、窓は小さくなります。
それでも、2011年に納入されたANAのボーイング787は、従来のボーイング767に比べ、約1.3倍という大きさでした。技術の進歩で窓の大きさも変わっていきます。
客室の窓に小さな穴が開いているわけ

客室の窓に小さな穴が開いているのをみたことありますか?穴は三重のアクリル板でつくられた窓すべてにあるわけではありません。中央の板にだけ、開けられています。この穴は、ブリードホールと呼ばれています。
先ほど与圧で窓には大きな負荷がかかっている話をしました。三重窓では、特に、真ん中と外側に圧力がかかります。一番客席側は、飾り板のようなものです。
そして真ん中の板に開いたブリードホールが、圧力を幾分和らげるんですね。一番外側の板にかかる圧力を、徐々に緩和させます。
エアバスによると、その穴が、客室と三層の窓の間のエアギャップを均等にするとしています。
また、この穴があることで、窓が曇りにくくなるようです。非常に小さい穴が、これほどまでの多機能だったとは!
気になる飛行機トリビア、『あなたも知っておいたほうがいい、飛行機の噂と真実5つ』『エコノミークラスの旅を快適に楽しむ方法10選。飛行機での長旅の参考に!』などもぜひチェックしてくださいね!
参考
[The alarming reason plane windows were changed from square to round|The Telegraph]
[Why do plane windows have tiny holes in them?|The Telegraph]
[航空豆知識|JAL]
[「ボーイング787」の注目は“窓”!? ANA仕様機をいち早くレポート|日経トレンディネット]