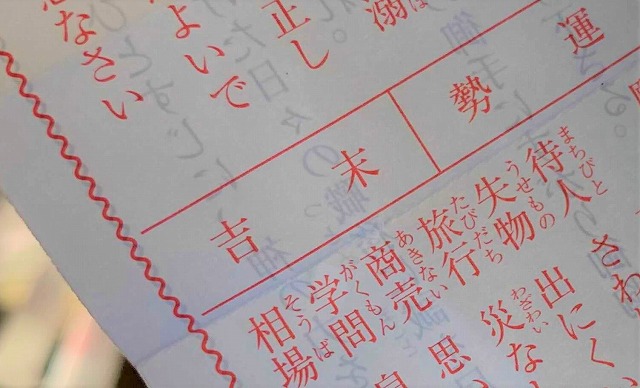福岡市
福岡県が発祥!観光におすすめのスポットも
ヤクルト

海外でも販売されているヤクルト製品
ヤクルトの歴史は、創始者である代田稔医学博士が、京都帝国大学医学部での研究の中で「乳酸菌シロタ株(L.パラカゼイ・シロタ株)」の強化培養に成功し、1935年に福岡市で「ヤクルト」の名称で発売したことに始まります。
その意図は、「予防医学」「健腸長寿」「誰もが手に入れられる価格で」という考えのもと、病気になってから治療するのではなく、腸を丈夫にして健康で長生きできるようにするというものでした。
戦後は販売組織が全国へと拡大し、1955年にはそれらを統括する「株式会社ヤクルト本社」を設立。1967年には研究拠点を京都から東京・国立市へ移し、研究開発体制を強化するとともに、「ジョア」などのはっ酵乳や清涼飲料、さらには化粧品・医薬品分野へと事業を広げました。
福岡市の「ホークスとうじん通り」沿いの一角には、ヤクルト容器を模した「ヤクルト発祥の地 記念碑」が建っています。福岡を訪れたら、ぜひチェックしてみてくださいね。
TOTO

トイレ
TOTO株式会社の始まりは、創業者・大倉和親氏が欧州で真っ白で清潔な衛生陶器に感銘を受け、「日本にも衛生陶器の時代が来る」と確信したことにあります。1912年に製陶研究所で国産化への挑戦を始め、試行錯誤を重ねた結果、1914年には国産初の腰掛式水洗便器を完成させ、1917年に北九州市小倉で前身となる東洋陶器株式会社を創設しました。
当時は水道設備も未発達で、衛生陶器の需要も限定的でしたが、技術者たちは欧州の製品を研究し、試作を重ねながら独自の焼成技術を確立。その結果、高品質で耐久性のある便器や洗面器が評価され、TOTOは日本の衛生環境の近代化を牽引する存在に。
1960年代以降は「ウォシュレット」など革新的な製品を次々と開発し、世界の水まわり文化を変革しました。今やTOTOは、世界へと展開する、日本を代表する衛生陶器メーカーへと発展しています。
TOTOのこれまでの歩みが知りたいのなら、「TOTOミュージアム」へ。TOTOを支えてきた食器のほか、衛生陶器・水栓金具・ウォシュレットといった貴重な展示が見られます。「超ミニチュア便器」などのオリジナルグッズも見逃せません。
とんこつラーメン

とんこつラーメン
福岡を代表するグルメ「とんこつラーメン」の発祥は、久留米市といわれています。1937年、屋台「南京千両」の宮本時男氏が、東京・横浜の支那そばや長崎チャンポンを参考に独自のスープを完成させたのが始まりとされています。
当初は比較的透明感のあるスープでしたが、1947年に同じ久留米の屋台「三九」で転機が訪れます。店主・杉野勝見氏の留守中、同氏の母がスープを強火で炊き続けた結果、乳化して白濁したそうです。味見するとコク深くまろやかで、その失敗ともいえる偶然の産物が現在のとんこつラーメンのスープのベースになりました。
現在、屋台「南京千両」は閉店しているものの、路面店「南京千両本家」は営業中です。ほかの久留米ラーメンとは異なり、ちぢれ麺で、細かく刻まれたチャーシューやメンマが特徴。どこか懐かしい味わいがくせになりますよ。また、JR久留米駅前には屋台の形をした「とんこつラーメン発祥の地碑」も。
福岡県久留米市野中町1357-15
うどん・そば(製粉技術)

そば
うどん・そば文化を支えた製粉技術の発祥地の一つとして知られるのが福岡市です。鎌倉時代の僧・聖一国師が宋から水力製粉の技法を記した「水磨の図」を持ち帰ったことで、粉を挽いて麺を作る文化が各地へと広がったとされます。
また、粉から作られる饅頭も博多で托鉢していた聖一国師(弁円/円爾)が茶店の主人に、中国で学んだ蒸し饅頭の作り方を伝えたのが始まりと伝えられます。
聖一国師が開いた承天寺の境内には、「饂飩蕎麦発祥之地」「御饅頭所」の石碑が建っています。
ロイヤルホスト(ロイヤルホールディングス株式会社)

ロイヤルホスト仙川駅前店
ロイヤルホールディングス株式会社の起点は、1951年に福岡空港で機内食搭載・喫茶営業を始めたことにあります。1956年には創業者・江頭匡一氏がケーキの冷凍技術を開発し、冷凍クリスマスケーキの製造販売をスタート。
1959年には、ファミリータイプのレストランの原点となる「ロイヤル新天町」を開業し、1962年に集中調理システム(セントラルキッチン)を導入しました。
1971年には北九州市でファミリーレストラン「ロイヤルホスト」1号店を出店。その後、全国展開とともにホテル事業、食品事業など多角化を推進。現在では海外展開も進めています。
起点となった福岡空港の喫茶は現在、業態が変わり「ROYALキャフェテリアMIYABI」として営業しています。福岡空港を利用する機会があったら、ぜひ立ち寄りたいですね。
福岡県福岡市博多区大字青木739 国際線旅客ターミナルビル 3F
公式サイト:https://www.fukuoka-airport.jp/shops/miyabi.html?utm_source=chatgpt.com
漫画『サザエさん』

西新中西商店街
「サザエさん」の作者・長谷川町子氏は幼少期、戦中・戦後を福岡で過ごしました。1945年頃、百道の海岸を散歩していた際に、漫画『サザエさん』の登場人物サザエ、カツオ、ワカメらの名前を思いついたと伝えられています。
翌1946年には、福岡の地方紙「夕刊フクニチ」で『サザエさん』の連載を開始。1992年には、漫画家として初めて国民栄誉賞を受賞しました。
福岡市早良区には、全長約1.6kmの「サザエさん通り」が整備され、「サザエさん発案の地」の記念碑が建てられています。その入り口にあたる脇山口交差点の南側には、西新商店街があり、昔ながらの商店や飲食店が軒を連ねています。
福岡県福岡市早良区
公式HP:https://www.city.fukuoka.lg.jp/sawaraku/sawaraku-tamatebako/kankou/sazaesan/index.html
独自文化と味わいの始まりが息づく福岡
福岡県には、地域ならではの独自文化や食の魅力が色濃く残っています。ヤクルトやTOTOといった生活を彩る企業文化、久留米で育まれたこってりとんこつラーメン、博多で伝えられたうどん・そばの製粉技術など、多彩です。伝統の味を楽しんだり、街の記念碑を巡ったりして、ぜひ福岡の始まりに触れてみてくださいね。
[All photos by PIXTA]