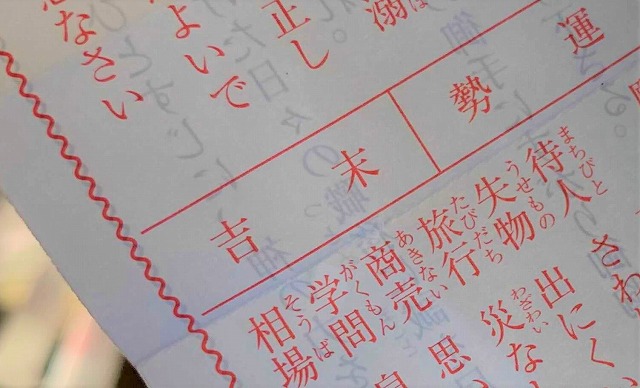志摩市・英虞湾
三重県が発祥!観光におすすめのスポットも
ベビースターラーメン

ベビースターラーメン
ベビースターラーメンは、津市に本社を構える株式会社おやつカンパニーが生んだ人気商品です。1948年、創業者・松田由雄氏が「おやつカンパニー」の前身となる「松田産業有限会社」を設立。
1950年代、即席麺の製造工程で生じた麺のかけらを無駄にせず味付けして社員に振る舞ったところ、「おいしい」と評判となり、商品化のきっかけとなりました。
そして1959年に「ベビーラーメン」として発売され、1973年には「ベビースターラーメン」へ改名。以来、時代に合わせたパッケージリニューアルや販路拡大を重ね、半世紀以上愛される国民的スナックへと成長しました。
ベビースターラーメンの魅力を存分に堪能したいのなら、横浜博覧館内にある「ベビースターランド」へ。できたてのベビースターラーメンが食べられるだけでなく、できあがっていく過程も見学できます。マグカップやトートバックといったオリジナル商品の購入も可能です。
海女

海女
伊勢志摩・鳥羽地域は、約2,000年前から海女が営まれてきたとされています。弥生時代の鳥羽市白浜遺跡からは大量のアワビ貝殻やアワビ漁具が発掘され、平安期の「延喜式」にも「志摩の潜女」として海女の存在が記録されているのです。
これらの歴史から、伊勢志摩は海女文化の発祥地のひとつとされ、現在も多くの海女がこの地で活動し、神宮への奉納や祭礼などの伝統を継承しています。
鳥羽・志摩には、海女をはじめ、海とともに生活する人たちの信仰を集める神社仏閣が多数存在。なかでも「海士潜女神社」は、潜水作業の「めまい除け」にご利益があるとされ、地元の海女や全国のダイバーから信仰されています。
オブラート

オブラート
薬を飲みやすくする発明品として、オブラートの歴史に新たな1ページを刻んだのが、三重県度会郡田丸(現・玉城町)の医師・小林政太郎氏です。
1902年、輸入され普及していた硬質オブラートの不便さに着想を得て、もっと簡単に飲める柔らかく薄いオブラート(柔軟オブラード)を開発。特許を取得するとともに、自ら「合名会社小林柔軟オブラート製造所」を設立し製造を開始します。
その後、1904年にセントルイス開催の万国博覧会で銅牌、1910年にロンドンの日英博覧会で金牌を受賞し、同氏が開発した柔軟オブラートは、世界へと広がっていきました。
小林政太郎氏の生家は現存。館内には資料などが展示されており、同氏の人生を辿ることができます。気になる方はぜひ訪れてみてください。
三重県度会郡玉城町佐田938
天むす

天むす ※画像はイメージです。
名古屋名物として広く知られる「天むす」ですが、実は津市大門にある「めいふつ天むすの千寿」が発祥です。1959年、津市大門伏見通りで天ぷら定食店を営んでいた初代・水谷ヨネ氏は、多忙で昼食を作る時間を確保できませんでした。
そのため、「せめて夫には栄養のあるものを」と車エビの天ぷらを切っておむすびの中に入れたのです。そして、それが夫や常連客からおいしいと喜ばれたため、試行錯誤を重ね、独自の味付けを生み出し「天むす」が誕生しました。
津市の「めいふつ天むすの千寿」では、お米一粒一粒がふっくらと炊き上げられた名物の「天むす」を味わえます。国内産高級ふきを丁寧に味付けしたきゃらぶきにも注目を! 津市を訪れたら、ぜひ立ち寄りたいですね。
手こね寿司

手こね寿司 ※画像はイメージです。
三重県を代表する郷土料理のひとつ「手こね寿司」は、志摩地方南部が発祥とされています。漁師が獲れたてのカツオを薄切りにして醤油に漬け、酢飯と手で和えて食べたのが始まりと伝わりますが、大漁祝いのハレの料理だったという説もあります。
志摩市内には、手こね寿司を提供するお店が点在。昔ながらのシンプルなものから伊勢海老を使った豪華なものを提供するお店までさまざまです。
なかでも1831年に料理旅館として創業した「すし久」がおすすめ。丁寧に仕込まれたカツオは臭みがなく、柔らかい酢飯とのコラボがたまりません。ショウガのほのかな香りもアクセントに! おかげ横丁に位置するため、伊勢神宮参拝ついでに訪れやすいのも魅力です。
真珠の養殖

アコヤ貝と真珠
真珠養殖の始まりは、三重県鳥羽出身の御木本幸吉氏が天然真珠に魅せられ、人工的に育てられないかと挑戦したことにあります。志摩・英虞湾でのアコヤ貝増殖を経て、1893年に鳥羽の相島で初めて半球状の養殖真珠を生産することに成功。1907年、見瀬辰平氏や西川藤吉氏らによって真円真珠の養殖技術が確立され、現在の真珠養殖の礎が築かれました。
「真珠工房 真珠の里(山本水産有限会社)」では、アコヤ貝の中から真珠を取り出してアクセサリーを作ることができます。世界でひとつだけのピアス、ペンダント、リング、タイピンなどをぜひ作ってみてくださいね!
三重県は文化と味覚の始まりの宝庫!
三重県は、古くから人々の暮らしとともに独自の文化や食の知恵を育んできた始まりの宝庫です。国民的おやつとして愛され続けるスナック菓子や、漁師町から生まれた豪快な郷土料理、さらには世界へと羽ばたいた革新的な発明や技術まで、実に多彩。三重県を訪れたら、ぜひ興味を引かれる始まりに触れてみてください。
[All photos by PIXTA]