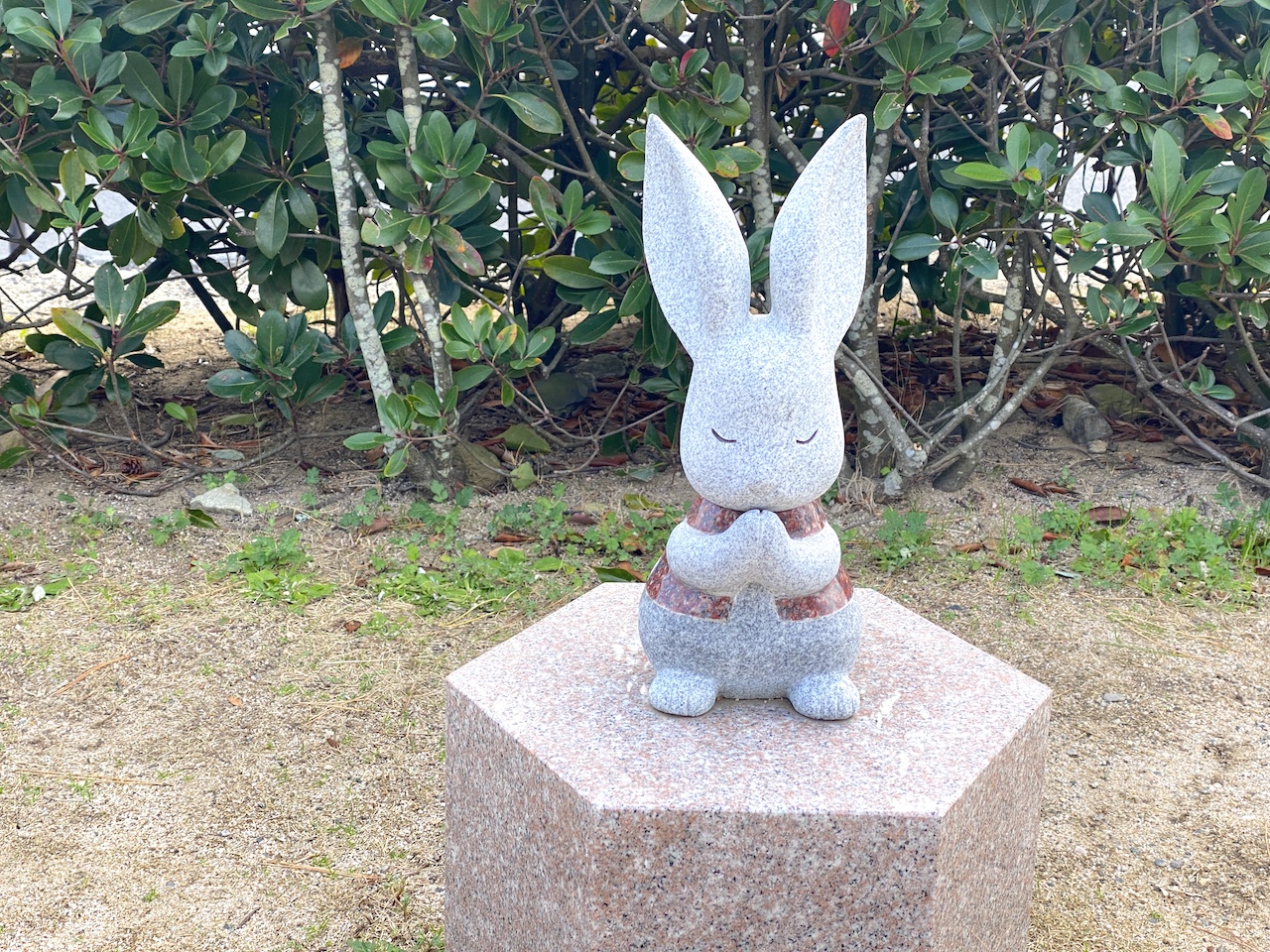宍道湖の湖畔
島根県が発祥!観光におすすめのスポットも
日本酒
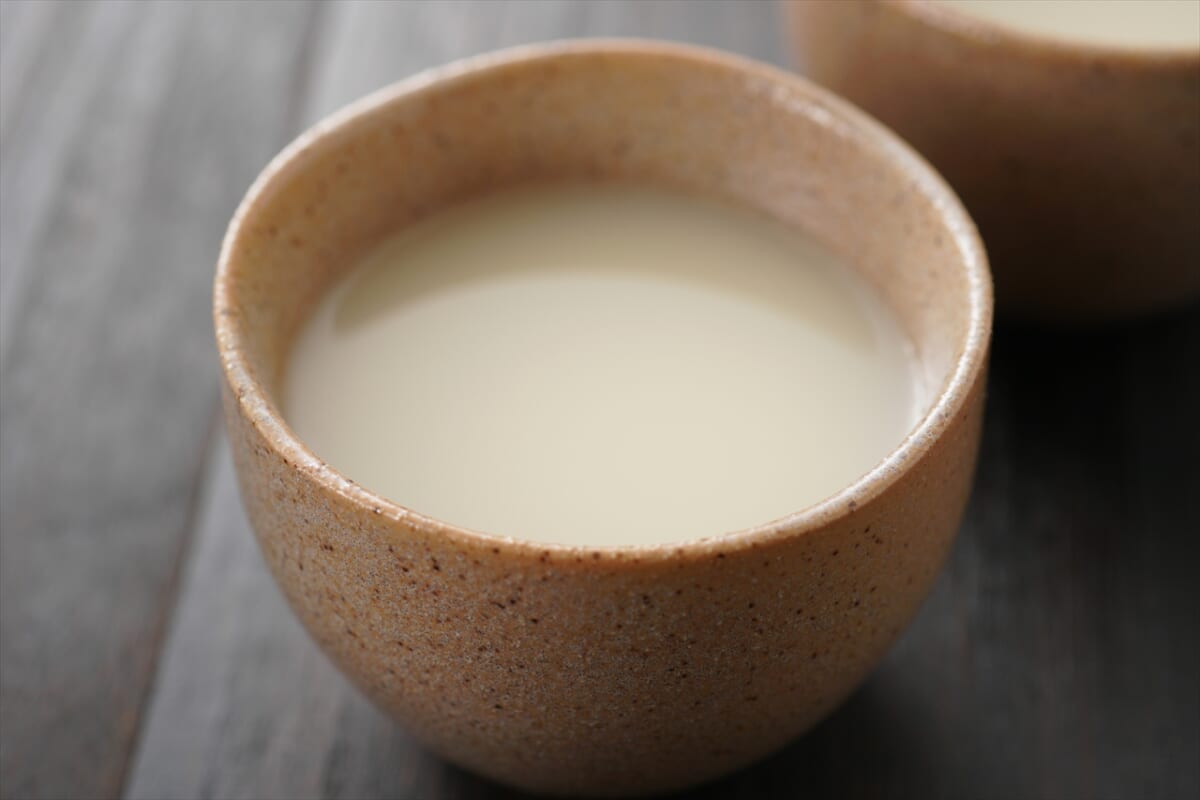
濁酒(どぶろく) ※画像はイメージです。
出雲市の「佐香神社(松尾神社)」は、日本酒発祥の地として知られています。奈良時代に編纂された『出雲国風土記』には、「この地(佐香郷)に神々が集まり、酒を醸して180日にわたり酒宴を開いた」との記述が残っているのです。
さらに、「佐香」は「酒」の語源となる言葉であることからも、この地が日本酒発祥の地であると考えられています。
佐香神社(松尾神社)には酒造りの神様「クスノカミ」が祀られていて、古くから全国で酒造りに携わる人たちの信仰を集めてきました。
特筆すべきは、神社として年一石(約180リットル)の酒造許可を持っている点。毎年10月13日の例大祭では、境内で仕込まれた濁酒が奉納され、参拝者は御神酒をいただくことができます。気になる方はぜひ訪れてみてくださいね。
島根県出雲市小境町108
公式HP:https://www.shimane-jinjacho.or.jp/izumo/1beb123ab8f871663770977d557a68b11a569622.html
ぜんざい

ぜんざい ※画像はイメージです。
ぜんざいの発祥地は、出雲地方といわれています。旧暦10月の神事「神在祭(かみありさい)」の際にふるまわれていた「神在(じんざい)餅」が、出雲弁(ずーずー弁)で訛って「ずんざい」、さらに「ぜんざい」と呼ばれるようになり、京都へと伝わったのが始まりとされているのです。
この説を裏づけるように、江戸時代の文献『雲陽誌』『祇園物語』『梅村載筆』にも、出雲がぜんざい発祥の地であることが記されています。
また出雲地方では、正月行事にも独自の食文化が残っており、元旦には岩海苔入りのすまし雑煮を、2日目には小豆雑煮を食べる地域もあります。
島根で本場の味を楽しむなら、「日本ぜんざい学会 壱号店」へ。大粒の大納言小豆に紅白の団子を浮かべた「出雲ぜんざい」や、ふっくら焼いた餅が香ばしい「縁結ぜんざい」など、出雲ならではの縁起の良い甘味が堪能できます。
島根県出雲市大社町杵築南775-11
公式HP:https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/chouju/restaurant/nosmokingrestaurant/izumo-keniki/izumo27.html
八尺瓊勾玉

玉造温泉の勾玉
歴代天皇に受け継がれる「三種の神器」のひとつ「八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」の起源は、玉造温泉にあると伝えられています。
古代の出雲では弥生時代から玉作りが始まり、松江市玉湯町玉造の花仙山(かせんざん)では、硬くてきめ細かい青めのうや、深みのある緑色の碧玉(へきぎょく)が豊富に採れることがわかっているのです。
そのため、この地は平安時代にかけて玉作りの一大産地として発展し、町内には30か所以上の玉作遺跡が残されています。
奈良時代に編纂された『古事記』にも「勾玉」にまつわる神話が登場し、玉造の歴史がいかに古く、神話の時代と深く結びついているかを物語っています。
勾玉について詳しく知りたいのなら「松江市出雲玉作資料館」がおすすめ。玉作りの工程や出雲との関わりを、展示を通してじっくり学ぶことができます。
さらに、勾玉の神を祀る「玉作湯神社」には、スサノオノミコトがヤマタノオロチ退治の褒美として授けられたと伝わる勾玉が祀られており、今もなお神話の気配を感じられる神秘的な地となっています。
島根県松江市玉湯町玉造99-3
公式HP:https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkasportsbu_bunkazaika/rekishi_bunkazai/1/3447.html
天叢雲剣

JR出雲市駅北口にある像
現在、愛知・熱田神宮に祀られている「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」、別名「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」の起源は、御立藪(おたてやぶ/現・雲南市の尾留大明神旧社地)と伝えられています。
この地で、スサノオノミコトがヤマタノオロチの尾を開いて「天叢雲剣」を得たという神話が語り継がれているのです。
神話の舞台とされる尾留大明神旧社地には、「尾留大明神天叢雲剣発祥地」と刻まれた記念碑が建ち、厳かな雰囲気が漂っています。
また、御立藪は尾留大明神として崇拝されていましたが、斐伊川の氾濫のため約200m南方に移され、「御代神社」として再興。その後、さらに500m南方に遷座しています。
島根県雲南市加茂町三代522
公式HP:https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/shiseijouhou/pr/shihou/23nenshihou11/510dfb18020.html
和歌

須我神社
和歌の発祥地と伝えられるのが、雲南市大東町須賀の「須我神社」です。この地でヤマタノオロチを退治したスサノオノミコトが「八雲立つ 出雲八重垣 つまごみに 八重垣つくる その八重垣を」と、日本で最初の和歌を詠んだといわれています。
また、スサノオノミコトとクシナダヒメがともに鎮まる「日本初之宮(にほんはつのみや)」としても名高く、境内には「和歌発祥の社」と刻まれた碑が立ち、神話のロマンを今に伝えています。神々の息吹と豊かな自然が調和する、出雲で屈指のパワースポットです。
安来節(どじょうすくい踊り)

安来節演芸館
「あら、えっさっさー」の掛け声で知られる「安来節(どじょうすくい踊り)」の発祥地は、安来市です。その起源は江戸中期にさかのぼります。当時の安来のまちでは民衆の間で歌舞音曲が流行し、七七七五調の歌詞で唄われる節回しが生まれ、現在の安来節の原型になったといわれているのです。
江戸後期には、安来港が米や鉄の積出港として発展し、北前船をはじめとする船舶の往来が活発に。全国の船頭たちとの交流を通じて各地の民謡文化が交わり、安来節もその影響を受けながら今の形へと洗練されていきました。
明治時代の終わりには、「渡辺お糸」という唄の名手が登場し、全国にその名を広めたと伝えられています。
現在、「安来節演芸館」では、本場の安来節を間近で楽しむことができます。1公演につき5名まで「どじょうすくい体験」も可能です。
島根は神話と文化が息づく始まりの地
神話の舞台となった島根県には、日本酒やぜんざい、勾玉、和歌、さらには安来節など、暮らしや文化を彩る発祥が今も色濃く残っています。豊かな自然と神話、そして職人の技が融合する島根を巡れば、古くから脈々と受け継がれてきた始まりの物語を辿る旅が楽しめるでしょう。
[All photos by PIXTA]