
秋田県が発祥!観光におすすめのスポットも
龍角散

※画像はイメージです。
今も多くの人に愛されているのど薬「龍角散」が誕生したのは、約200年前の江戸時代末期。秋田藩(現・秋田県一帯)で藩主に仕えていた御典医・藤井正亭治(しょうていじ)が、喘息に苦しむ藩主のために開発したのが始まりです。藩に伝わる咳止め薬に、漢方や蘭方医学の知見を取り入れ改良を重ね、現在の龍角散の原型となる薬を作り上げました。
明治維新後、龍角散は御典医だった藤井家に正式に下賜されます。藤井正亭治(3代目)は藩主とともに江戸へ移り、現在の東京都千代田区東神田付近に薬屋を開業。1871年に「龍角散」の一般販売を開始し、国民的な薬として広く愛されるようになりました。なお、名前の由来は、当時配合されていた「龍骨」や「龍脳」「鹿角霜」といった生薬にちなむものです。
東京都千代田区東神田にある「龍角散ビル」では、「龍角散ビルコンサート」を開催。入場無料(要予約の場合あり)なので、音楽好きも要チェックです。
東京都千代田区東神田2-5-12
いぶりがっこ

秋田を代表する燻製たくあん「いぶりがっこ」は、県内陸部の農家で古くから作られてきた郷土食。内陸南部では降雪と寒冷のため天日干しが難しく、農家では囲炉裏の煙で大根を乾かす工夫がされました。この囲炉裏干しのたくあんこそ、「いぶりがっこ」の原型です。その起源は室町時代ともいわれています。
現在では、保存食として家庭で作る人は減ったものの、物産品としての生産が広がり、県内全域で作られるように。直売所やスーパー、ネット通販などでも購入可能になりました。2017年には「秋田県いぶりがっこ振興協議会」が設立、2019年にはGI(地理的表示)にも登録。秋田ならではのブランドとして守られています。また、いぶりがっこの名前の由来は、「いぶり」は「いぶした」、「がっこ」は「漬け物」を意味する秋田の方言です。
横手市山内地域では「いぶりがっこ」の製造作業体験ができます。見学のみも行っているそうなので、興味がある方は問い合わせてみてください。
秋田県横手市山内筏字小田野沢34
公式HP:https://yokote-kankou.jp/kankou-expert/ex/%E3%80%8C%E3%81%84%E3%81%B6%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%93%E3%80%8D%E8%A3%BD%E9%80%A0%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82/
あきたこまち
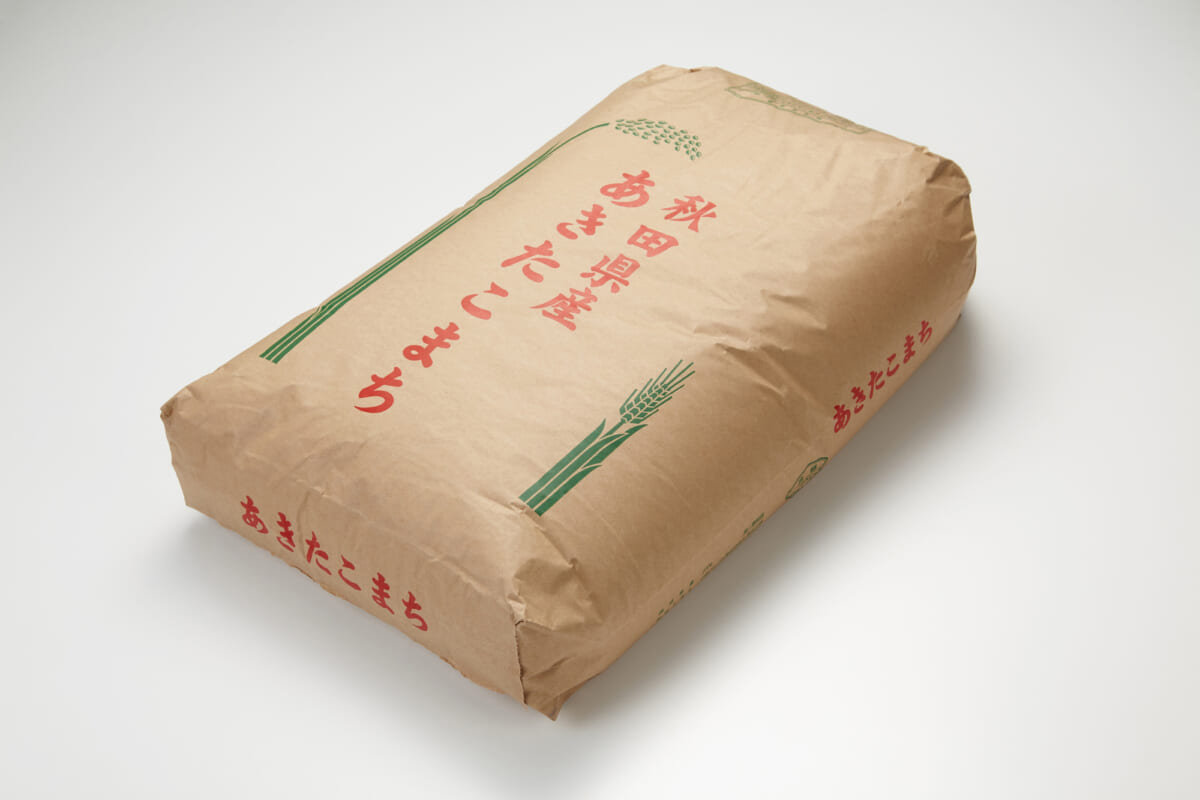
秋田を代表するブランド米「あきたこまち」が生まれたのは、秋田県農業試験場。1977年から始まった育種作業により、福井県農業試験場から譲り受けたコシヒカリ系統と奥羽292号を掛け合わせ、寒冷な秋田にも適した「秋田31号」を完成させました。この品種は、食味に優れ、早熟性があり、かつ倒伏にも強いのが特徴。平安時代の歌人・小野小町にちなんで「あきたこまち」と命名され、1984年にデビューしました。発売直後、日本穀物検定協会による食味試験でも高評価を獲得し、全国でもトップクラスの人気米に!
大仙市にある「秋田県立農業科学館」の第二展示室には、あきたこまちが誕生するまでの過程が展示されています。テラスで栽培したそれぞれの稲を標本も! さらに秋田県の農業の過去・現在・未来を学べるほか、熱帯温室、果樹園や曲屋といった施設も充実しています。大仙市を訪れたら立ち寄りたいですね。
忠犬ハチ公

秋田犬
渋谷駅前の銅像で有名な「忠犬ハチ公」は、秋田県大館市出身の秋田犬です。1923年、大館市大子内(おおしない)の斎藤義一氏の家で、父・大子内山号、母・ゴマ号の間に生まれました。当時、東京帝国大学農学部教授の上野英三郎博士が日本犬を探しており、教え子を通じて斎藤家から生後約50日の子犬を譲り受けたのが「ハチ」です。
大館市観光交流施設「秋田犬の里」には、渋谷駅のハチ公像をモデルとして建てられた、もうひとつのハチ公像があります。館内には、秋田犬の特徴や歴史を学べる秋田犬ミュージアムや、可愛い秋田犬をガラス越しで見学できる秋田犬展示室のほか、秋田県グッズが購入できるお土産コーナーも。秋田犬好き垂涎のスポットです。
ロケット

※画像はイメージです。
1955年、秋田県由利本荘市の海岸で、東京大学生産技術研究所の糸川英夫博士が国内初となる固体燃料ロケット「ペンシルロケット」の打ち上げに成功しました。その後、2段式の「ベビーロケット」や、大型の「カッパロケット」など、さまざまな実験を実施。しかしロケットの飛行高度が上がるにつれ、大陸に落下する危険性が懸念されるように。陸・海・空の安全を考慮し、1963年、実験場は鹿児島県内之浦町(現・肝付町)へ移設されました。
秋田県由利本荘市岩城には、宇宙開発の父と呼ばれる糸川英夫博士のペンシルロケットの打ち上げの功績を讃えた「日本ロケット発祥記念之碑」が建っています。この碑と空を交互に眺めながら、宇宙に想いを馳せたいですね。
秋田県由利本荘市岩城勝手
なまはげ

男鹿地域の伝統文化「なまはげ」は、1978年に日本の重要無形民俗文化財に指定されました。発祥時期や起源は明らかになっていませんが、最古の記録は1811年。旅行家・文筆家の菅江真澄が旅行記の中で、恐ろしい神の使いとの遭遇を文字と挿絵で紹介しており、その描写には仮面や子どもを脅す様子など、現代のなまはげと重なる点が見られます。かつて、なまはげ行事は小正月(2月中旬)の夜に行われていましたが、1873年に日本がグレゴリオ暦(新暦)を採用したため、現在は12月31日に実施されています。
なまはげについてさらに深く知りたい方は「なまはげ館」へ。男鹿市各地で実際に使われた150点以上の多彩ななまはげ面を見学できるほか、民具や映像、パネル展示を通じて、男鹿の風土と文化を学べます。オリジナルのなまはげグッズも購入可能です。
秋田の「はじまり」は個性的で心を動かされるものばかり!
秋田には、忠犬ハチ公をはじめ、あきたこまちやなまはげなど、触れるたびに感動や驚きを与えてくれる「はじまり」が数多く存在します。そんな個性豊かな秋田の地から、これからどんな新たな「はじまり」が生まれるのか、目が離せませんね。
[Photos by PIXTA]









