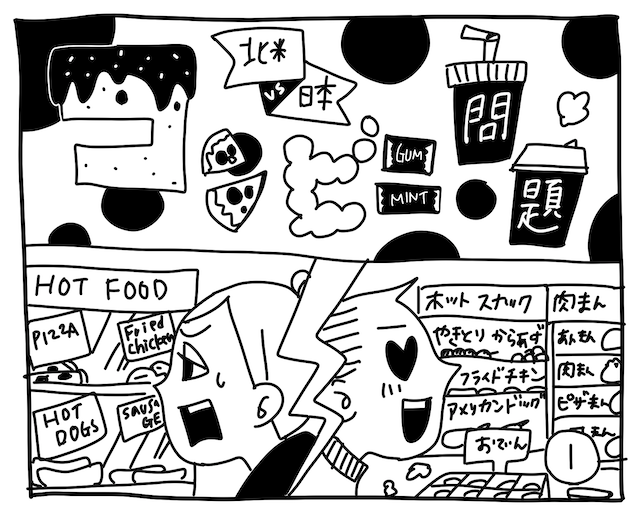ステンレス製の魔法瓶は日本で誕生した

旅の愛用品に水筒を欠かさない人も多いと思います。水筒といってもいろいろありますが、「ステンレス製の魔法瓶」といったら、どこのメーカーを思い浮かべますか?
「象印」でしょうか。「タイガー」でしょうか。はたまた「サーモス」でしょうか。今では当たり前に人々の暮らしに溶け込んでいるこのステンレス製魔法瓶は、日本で初めて誕生したのでした。
もともと魔法瓶のアイデアは海外で考案されました。1880年代に、ドイツの物理学者が真空構造の容器を考え付き、イギリス人の科学者がガラス製の魔法瓶を1892年(明治25年)に考案します。
ガラス製の魔法瓶とは真空二重構造のガラス製容器ですが、次いで、このガラス容器を金属ケースで覆うアイデアが1904年(明治37年)に誕生します。そのアイデアの特許がドイツで取得され、考案者はテルモス有限会社を設立しました。
魔法瓶のブランド名にもなった「テルモス」は、ギリシア語で「暑熱」といった意味を持ちます。つづりはTHERMOSで、英語読みでは「サーモス」。あのサーモスの誕生ですね。
その後、イギリス・アメリカ・カナダに事業が展開され、世界で広がりを見せていきました。
ガラス製だった魔法瓶をステンレス製として提案

魔法瓶の次の進化は、ずっと遅れて1978年(昭和53年)になります。「日本酸素」という日本企業が、長らくガラス製だった魔法瓶をステンレス製として提案します。
もともと日本酸素は工業用ガスメーカーです。製鉄所や半導体工場で使われる工業用ガスを扱う会社でした。
「なんでそんな会社が魔法瓶づくりに乗り出したの?」と思いますよね。
毎日新聞経済部『増補版 日本の技術は世界一』(新潮社)によると、1975年(昭和50年)ごろ社内に、
<「真空技術を生かせる新商品を探せ」と新規事業開拓チームが生まれた>(『増補版 日本の技術は世界一』より引用)
ということのようです。
工業用ガスは、氷点下200℃くらいに冷やし液体にして、ステンレス製の真空二重構造にした筒型タンクに入れて運びます。路上で見かけるあの巨大なタンクローリーですね。輸送時にガスの温度が上がって気化したら爆発事故も起きかねないからです。
この技術を何かで生かせないかと新規事業開拓チームが立ち上がり、そのメンバーの1人・里見泰彦さんが街を歩き回っている時、ガラスの魔法瓶を落として泣いている子どもを見かけました。
その悲しそうな子どもの顔を見ながら、落としても割れない魔法瓶としてステンレス製魔法瓶を思い付きます。そのアイデアが「アクト・ステンレスポット」として1978年(昭和53年)に製品化されました。
その製品写真を見て思い出したのですが、1979年(昭和54年)生まれの筆者がおむつをはいて芝生の上でピクニックしている古い写真に、まさにこの「アクト・ステンレスポット」が写っています。うちの両親はも、世界初の高真空ステンレス製魔法瓶を購入していたのですね。
世界120カ国で愛され、世界シェアもトップクラス

とはいえ、国内市場を一気に独占できるほど甘くはなかったようです。その後も、1982年(昭和57年)発売の「シャトル・ミニ」などヒット商品は出たものの、国内シェアでは象印やタイガーに追い上げられ、国内では長らく苦戦したのだとか。
そこで、海外市場を一気に開拓するべく1989年(昭和64年/平成元年)にはガラス魔法瓶のシェアで世界一だったサーモスを買収します。イギリス・アメリカ・カナダにおけるサーモスの事業を買収し、サーモスブランドでステンレス製魔法瓶の普及に努めたのですね。
1990年(平成2年)にはサーモス事業部が社内に発足。日本酸素のサーモス事業部とステンレス製魔法瓶の製造を担ってきた日酸サーモが統合してサーモス株式会社が2001年(平成13年)に誕生します。
その後も同社は「真空断熱スポーツボトル」や「真空断熱ケータイマグ」、「真空断熱フードコンテナー(スープジャー)」といった革新的な商品を次々と市場に送り込みます。
さらには国内に直営店をつくり、海外にも関連会社を立ち上げて展開を続け、今の立ち位置を築いたのですね。
旅でも大活躍するステンレス製魔法瓶。日本が劇的に進化させたアイテムなのだと誇りに感じながら、世界へ一緒に連れ出してあげたいですね。
[参考]
※ サーモス(THERMOS)はなぜ「廃業寸前」から世界トップ企業になったのか? – 株式会社クリエート・バリュー
※ 日本酸素ホールディングスのあゆみ – 日本酸素ホールディングス
※ 毎日新聞経済部『増補版 日本の技術は世界一』(新潮社)
※ Thermos Co. to Be Sold to Japanese Firm – Los Angels Times
[Photos by Shutterstock.com]