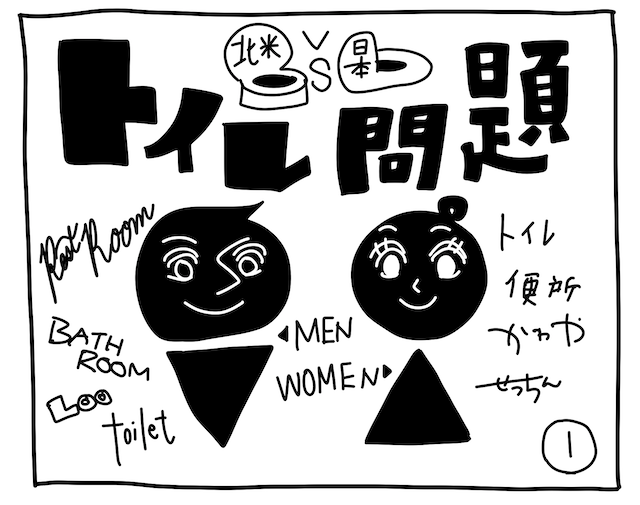気持ちよく年を越す、新年を迎えるには「挨拶」が大切!
一年の最後にその年、お世話になった人に「よいお年を」と相手を思うひとことを添えたり、新年に「あけましておめでとう!」と挨拶したりと、年末年始は、いつもより丁寧に挨拶したいものです。気持ちの良い一年が迎えるためにも覚えておきたい、年末年始の挨拶フレーズをご紹介します。
年末に使える「良いお年を!」

年末最後の別れ際に誰もが使う「よいお年を!」というひとこと、英語では次のように言えます。
Have a happy new year!
よい新年を!
Enjoy your rest of the year!
残り少ない今年を楽しんでね!
定番「あけましておめでとう!」

新年の挨拶は、やはりHappy new year!が定番です。道端で会った近所の人や、お店の店員さんなどにも一年の初めの数日はHelloの代わりにHappy new year!を使います。
また、「あけましておめでとうござます」とたいていセットで使われる「今年もよろしくお願いします」は、なんて言ったらいいでしょうか? 「よろしくお願いする」という日本的な含みを持たせた表現が、英語にはしっくりくるものがありません。自分に対して何かをお願いするというよりは、相手の幸せを願う挨拶が一般的です。
I wish you all the best for the new year.
新しい年があなたにとって素晴らしいものになりますように。
欠かせない年はじめの会話

日本より挨拶や世間話を大切にするイギリスでは、年明けそうそうに会った友達や仕事仲間とは、必ず新年の挨拶を丁寧にします。挨拶といっても日本のように「昨年は大変お世話になりました。今年もよろしく」というような内容ではなく、「クリスマス休暇はどうしてたの? 大みそかはパーティした?」のようなプライベートなお互いの近況をこと細かに、そして順番に話します。
例)Happy new year!
あけましておめでとう!
How was your Christmas?
クリスマスはどうだった?
It was great, thank! I went home for Christmas and came back to London on 30th.
最高だったよ、ありがとう! クリスマスには実家に帰って、ロンドンには30日に戻ってきたよ。
イギリスに限っては「クリスマス」を使ってOK!

ダイバーシティ(多様性)を重んじる世界的な流れから、特にアメリカではキリスト教でない人を尊重して「メリークリスマス」よりはHappy Holidaysが好まれる傾向があります。
ところが、筆者の住むイギリスに限って言えば、いまだに新年よりはクリスマスのほうが大きな祝日、イベントのため、あまり相手のバックグラウンドを配慮せずに「メリークリスマス!」と言うことが一般的です。
サリーをまとったインド系のご家族の知り合いが、おじいさんやおばあさんと総出で外出されているところに出くわした、というような場合は「クリスマス」という言葉を自然と使わずに済ませますが、イスラム教やヒンズー教の友人・知人でもイギリスで生まれ育って、イギリス内で教育を受けてきた人に対しては、もはや宗教を超えて「イギリスの文化、習慣」として「メリークリスマス!」と言っても、相手を不愉快にさせる心配は今のところ少ないように思います。
実際、クリスチャンでない日本人の筆者にも、ほとんどのイギリス人が「メリークリスマス!」と言ってくれたり、クリスマスカードを送ってくれます。
むしろ「この人は、クリスチャンじゃないかも?」と肌の色や人種から(勝手に)判断されてMerry Christmas!を使われないことに違和感を感じる人のほうが多いかもしれません。ただし、多国籍の人が集まるグローバルな場面では、やはり配慮も忘れずにいたいものです。
[All Photos by Shutterstock.com]